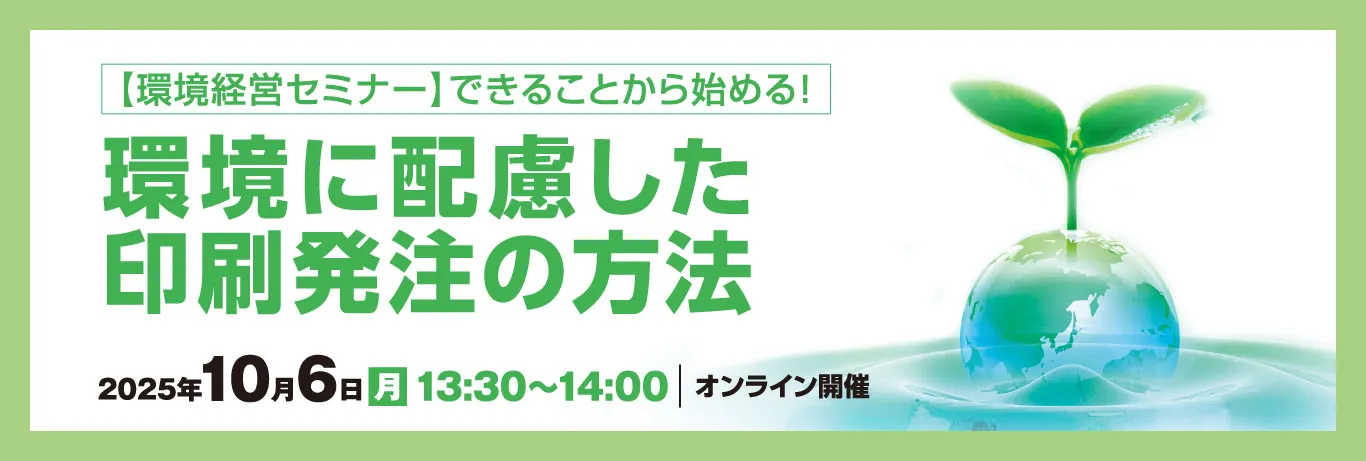「そだねー」や「知らんけど」といった方言由来のフレーズは定期的に流行しており、「~じゃん」のように全国的な表現として普及したものも少なくありません。
こうした方言はマーケティングやブランディングなどにおいても、印象を強めて差別化をはかる上で効果的な要素として活用できます。
今回は全国の方言を取り入れたプロモーションの成功事例や、方言をマーケティングに活用するメリットを紹介いたします。
方言を活用したマーケティング・プロモーションの事例
事例① 土佐弁 × キリンビール高知支社
高知では街のいたるところで「たっすいがはいかん(弱々しいものはダメだ)」という書かれたビールの広告を見かけます。
これはキリンビール高知支社が1990年代後半から用い始めたキャッチコピーで、当時競合商品に対抗しようとラガービールの風味を変えて販売した際に届いた「風味が薄く弱弱しくなってしまいダメだ」という不評の声がもとになっています。
キリンラガービールの消費量日本一だった高知の人たちの声を受けて、商品の風味を改善して上記のキャッチコピーを用いたキャンペーンを行ったところ、2001年にキリンビールが県内でビールの消費シェア1位となりました。
キリンビールは日本全国の支社ごとでキャンペーンを行っており、高知支社以外にも「つれもて飲むら!(紀州弁で「一緒に飲もう!」)」といった方言を用いたキャッチコピーを採用しています。
事例② 津軽弁 × 朝日放送グループ
2023年12月、青森県に芸人の顔とともに「時庭戻すべ(時を戻そう)」などと書かれたポスターが期間限定で設置されました。
毎年12月に全国ネットで放映される「M-1グランプリ」、2022年での世帯視聴率が一番高かった青森県にて同番組を方言で宣伝するポスターが貼られました。
県内12か所のポスターの位置を地図でつなぐと「M-1」の文字が浮かぶユニークな仕掛けが施されましたが、その際には文字が再現できる位置に掲載できる場所がないか実際に一つひとつ現地に行って回ったそうです。
またポスターは津軽弁を用いる県西部と南部弁を用いる県東部の両方で掲示されるため、掲載される場所の現地の方言にあわせてテキストも修正されています。
こうした細やかな工夫がほどこされた「M-1」のポスターは、放送局の公式SNSで投稿されると注目をあつめ地元のメディアでも特集されるほどとなりました。
事例③ 上州弁 × ぐんま方言カルタ
郷土カルタの元祖といえる「上毛かるた」で知られる群馬県で、2012年に上州弁を盛り込んだ「ぐんま方言カルタ」が発売されました。
2021年に発売された第2弾とともに地元の大学生が手掛けており、読み札には「はぁーけーるんきゃ?(もう帰るのか?)」といった方言だけでなく地元の文化についても載せられています。
方言の保存を目的に開発されたもので県内の書店や旅館などで販売されたところ1万部の大ヒットを記録し、全国にある方言カルタのパイオニア的な存在となりました。
第2弾では専用のアプリにより地元テレビ局のアナウンサーが読み札を読み上げた音声を流すことで、より実際の方言を体感できるようになっています。
現在では小学校などの教材としても導入されており、若い世代に方言を伝承するツールとしても活用されています。
事例④ 琉球方言 × 「沖ツラ」
2020年に連載が始まった「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」(以下、沖ツラ)は沖縄の方言や文化を取り上げたコミック作品で、現地でも高い人気を得ています。
内容は作者が実際に現地に移住して体験したことが中心で、「あいえーなー、チラしに赤い!(なんてことだ、顔がすごく赤い!)」といった方言のセリフも数多く登場します。
現地のことを丁寧に描写した作品性が現地で評価され、単行本が販売されると県内では有名作品を超える売り上げを記録し、漫画本で初めて地元の書店大賞に受賞するほどとなりました。
2025年1月にアニメ化された際には舞台となるうるま市で観光促進のためのクラウドファンディングも行われ、目標金額の300万円の3倍近くもの金額が集まりました。
他にも舞台をめぐる観光ツアーのパックや、地元の自治体のふるさと納税などといったコラボ企画が県内で次々と実行されており、経済的な盛り上がりも見られています。
事例⑤ 全国の方言 × ご当地Tシャツ
「おばんです」「しょったれ」「はがやしい」…ここ数年、こうした方言のフレーズをデザインにしたTシャツが全国で売られるようになりました。
もともとこうしたTシャツは土産物として観光客向けのものが多く、2023年に青森県内のドンキホーテで売られた津軽弁のTシャツも当初は土産としての販売を想定していました。
しかしSNSを中心に地元住民の間で話題となり地方紙や地方局にとりあげられると、多くの県民の支持を得るヒット商品となっていきました。
現在では北海道から沖縄まで全国の店舗にて、現地の方言がデザインされた方言Tシャツがご当地限定商品として売られています。
地元愛の強い地域では他のパロディTシャツよりも人気を博しており、2025年高知の店舗で販売された「おじた(驚いた)」と書かれたTシャツは販売後18分で完売するといったことも起こっています。
方言をマーケティングに活用する主な3つのメリット
ターゲットに親しみやすさでアプローチできる
慣れ親しんだ地元の方言をコミュニケーションに用いることで、標準語よりも相手に親近感や安心感を与えて注意を自然な形で引き出しやすいといえます。
そのためマーケティングにおいても相手の心理的なハードルを下げて商品や会社に興味を持ってもらうきっかけとして、方言を有効活用することができます。
ほかの地方から来た人には「方言でもてなすことによる暖かみ」、地元の人には「自分たちの方言を使っていることでの共通意識」を感じてもらうことで購買意欲やブランド認知につなげられます。
SNSやネット上で話題となりやすい
標準語が多く用いられているマーケティングのフレーズにおいて、方言のフレーズはほかにはないインパクトを出すことができます。
方言のフレーズをでかでかと表していることで、一目見ただけでどういう意味か気を引きやすくSNSやネットで話題を集めやすいといえます。
このため少ない予算でも多くの人の興味をひきやすく、広告費をおさえて効率よく認知を広めるプロモーションをかけることも可能です。
方言を使う地元からの支持を集めやすい
プロモーションで方言や地元民が共感できる話題を用いることで、「自分たちの文化を理解してくれれている」と感じてもらえる可能性があります。
方言ではありませんが埼玉県民の「あるある」を丁寧に作品に反映させた「翔んで埼玉」は、埼玉を自虐した内容ながら強い県民からの支持を得ています。
このように地元住民が共感できるよう自然な形で方言を使うことで、「この企業やブランドは自分たちの地元を重視してくれている」と感じてくれるでしょう。
方言をマーケティングに活用する上での主な注意点
地元民が不快に感じる表現や用法を避ける
方言の中には、他の地方の人にはわかりづらい微妙なニュアンスや意味の違いのあるものも少なくありません。
意味を深く調べずに方言の言い回しを軽率に使ったら、実は侮辱的な意味にとらえられる可能性がある言葉だったということもあり得ます。
方言をただ使うだけでなく、その言葉の背景知識もきちんと調べたうえでフレーズとして用いるべきかを事前に慎重に検討する必要があります。
不自然な表現だと思われないようにする
ローカル色を出そうとして方言を過剰に用いて演出しようとすると、実際の方言のかたちとかけ離れてしまいかえって違和感が出てしまうこともあります。
そのためには先入観などではなくきちんと地元民が実際に使う様子を調べて、リアルな方言の姿を取り入れることが重要です。
また映像コンテンツなどに方言を使う際は、きちんと現地のイントネーションに則って方言を用いているか意識することも大切です。
若い世代や他地域の方にも伝わりやすくする
方言の中には若い世代にも通じる言い回しとそうでないものがあるため、マーケティングでもどの層をターゲットにするかによって用いるフレーズも変わってきます。
特に古い表現になじみのない若い世代や他県からの観光客などをターゲットにしている場合、あえて難解なフレーズを用いてインパクトを出すのも手ですが、親しみやすさを演出するにはある程度若い世代でも通じる方言を用いることが有効といえます。
方言によるマーケティングは対内的にも効果あり!
方言を用いたプロモーションと聞くと、都市部から来た観光客に行うイメージがあるかもしれませんが、実はその方言を使う地域住民にも十分活用できます。
最初は方言の保存や観光での販売を目的としたものも、いつのまにか県内で人気を集めだして気が付いたら地元のヒット商品となったという例も少なくありません。
ただ方言には歴史的な背景や微妙なニュアンスの違いなどもあるため、ただ適当に用いただけでは地元からの共感や指示を得られる可能性は低いでしょう。
きちんと地元の人の話し言葉を調べて、実際の方言のかたちをマーケティングやプロモーションに活かすという考えが何より重要だといえます。