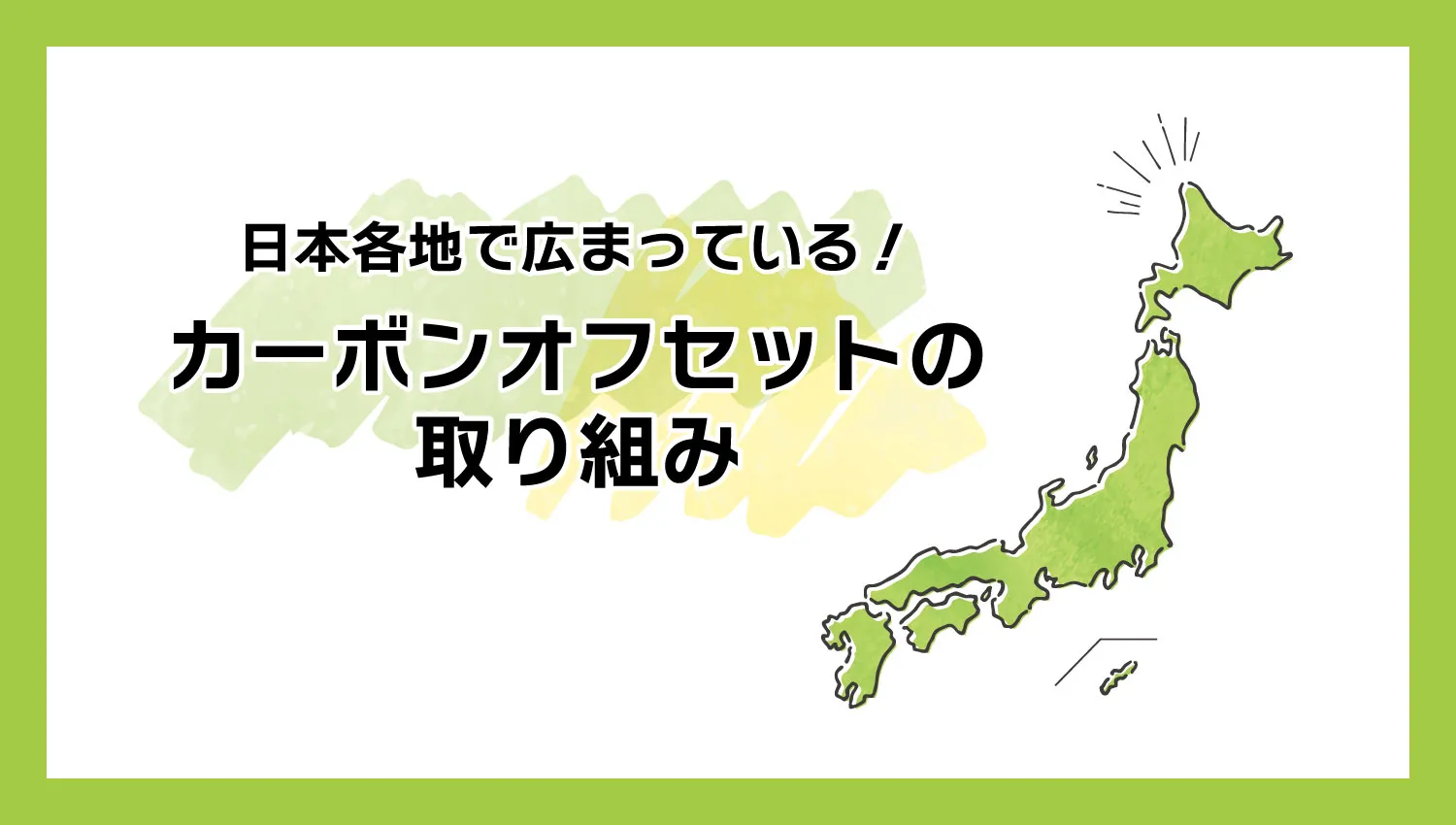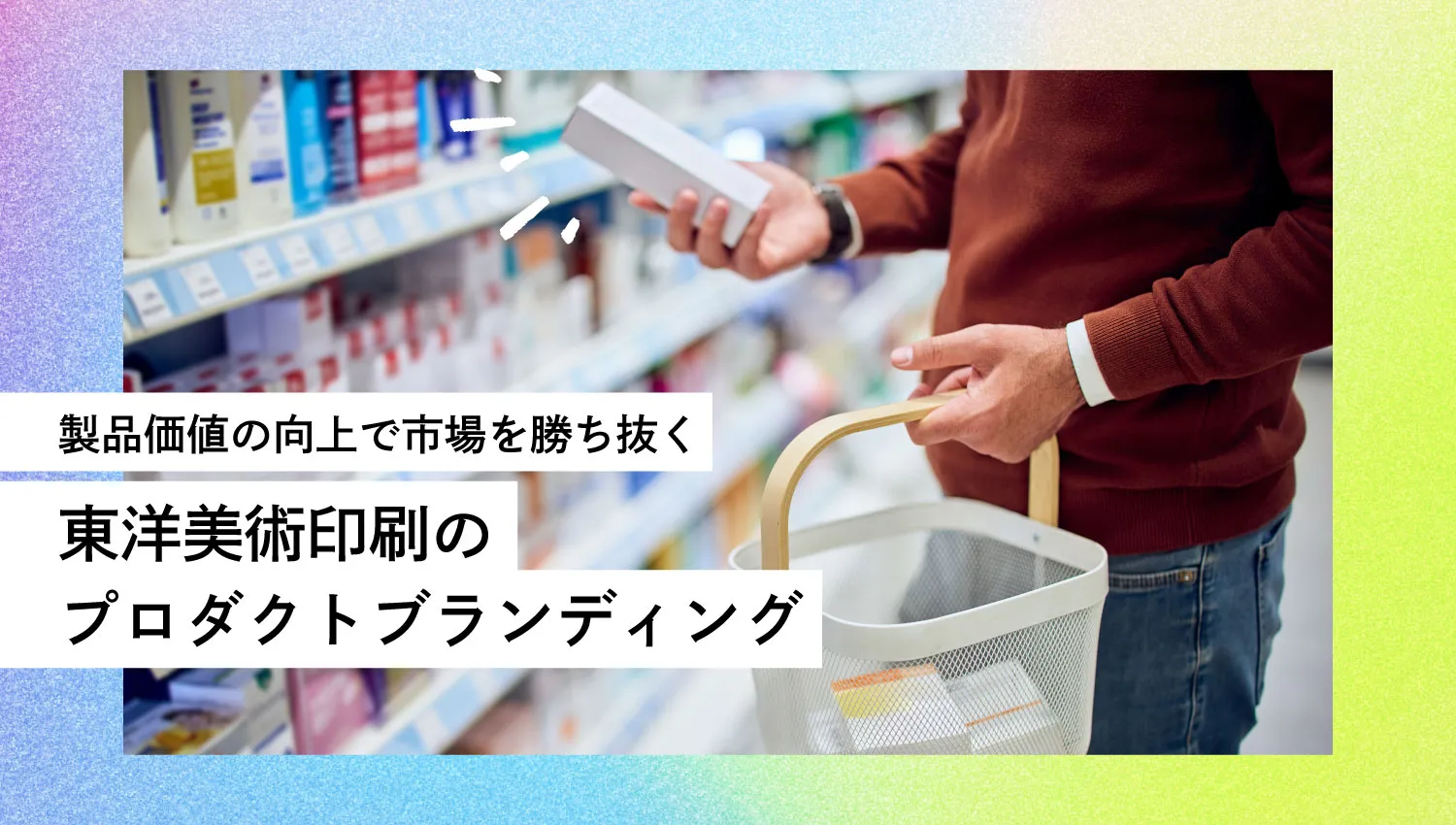カーボンオフセットは日常生活において発生する温室効果ガスに対して、脱炭素化や環境保全につながる取り組みに支援することで発生分を相殺する制度です。
CO2排出量の削減にはできる範囲があるため、企業や自治体がカーボンオフセットを行う事例は国内外で多く見られています。
実はカーボンオフセットに取り組むことで、ブランドイメージの向上などの効果も期待できます。
そこで今日はカーボンオフセットについて、最新の取り組み事例を中心に紹介します。
カーボンオフセットとはどういう制度なのかおさらい
カーボンオフセットは民間企業などが排出するCO2の排出量に応じた枠のクレジット(排出権)を自治体などから購入することで、売却資金を現地の植林活動や再生可能エネルギーの普及などの取り組みに充てるというものです。
植林などを行った団体や企業は吸収・削減できるCO2の量を算出したのち、クレジットを運用する団体にカーボンオフセットのプロジェクトとして認可を申請します。
その後、民間企業が工場での生産や輸送などで出てしまうCO2の量に応じたクレジットを運用団体から購入することで、排出量をオフセットするという仕組みです。
国内で一番広く活用されているクレジットとして環境省などが運用している「J-クレジット」があり、2025年8月時点で全国の1200件以上の環境保護プロジェクトがJ-クレジット創出の認可を得ています。
そのほかにも地方自治体が発行している地域版J-クレジットというものもあり、2025年現在は高知県版と新潟県版のJ-クレジットが創出されています。
クレジット創出に関する国内の近年の事例
山梨県、国内最大規模の森林クレジットの提供を計画
2025年5月、山梨県は三井物産と県の面積の3分の1を占めている県有林を活用したJ-クレジット制度を創出するための協定を結びました。
協定では県が適切に管理した森林に関して、樹齢や樹種などの情報や航空レーザーによる分析データを提供して、三井物産が環境活動のプロジェクトを計画してクレジットを販売するといったフローが取り決められました。
これにより14.5万ヘクタール(東京23区の2倍以上の面積)の県有林を活用した128万t-CO2分ものクレジットを創出でき、これは国内で最大規模となります。
現在、県と三井物産が共同でカーボンオフセットのプロジェクト登録の手続きを行っており、早ければ2026年にクレジットとして提供される予定です。
モズク養殖事業によるクレジットの創出が認可される
2025年1月、沖縄県うるま市・TOPPANデジタル・勝連漁業協同組合はモズクの養殖事業を通じて創出されたブルーカーボン・クレジットに関してカーボンオフセットの認証を取得しました。
ブルーカーボンとは海洋生物が光合成で吸収するCO2のことで、このクレジットでは3年間で養殖モズクが吸収した21.7トン分のCO2が対象となっています。
クレジット売却で得られた収益はモズク養殖の維持や藻場の保全、担い手が不足している地域の漁業の活性化などといった活動にあてられる予定です。
このほかにも勝連漁業協同組合では天然胞子を用いた方法を導入することで、養殖生産を通じて排出されるCO2の削減にも取り組んでいます。
日本初となる国際クレジット取得に向けた締結
2024年9月、静岡県浜松市と双日などの8社の企業は市有林の日本初の「ボランタリークレジット」認証取得に向けて連携協定を締結しました。
ボランタリークレジットは民間での認可によるクレジット認証制度で、浜松市はその中でも特に世界的に利用されている「VCSクレジット」の認証を目指しています。
静岡県浜松市は面積の3分の2が森林地帯であり、古くから市や地元の企業が積極的にFSC®認証を取得するなど森林保全への取り組みが行われています。
従来のJ-クレジットに加えてボランタリークレジットの認証を取得することにより、浜松市は古くからの林業地帯である市内の森林の価値向上を目指しています。
クレジット活用に関する国内の近年の事例
東武バスグループ、カーボンオフセット燃料を導入
東武バスグループの東武バスセントラルは2025年6月、路線バスの車両に使われる燃料の一部でカーボンオフセット燃料を導入しました。
今回導入したカーボンオフセット燃料は出光興産が販売したもので、軽油を利用したときのCO2排出量分をクレジットの購入によりオフセットするというものです。
千葉県柏市にある同社の営業事務所にて利用されはじめており、カーボンオフセットによりCO2排出量を年間で約1500トン削減できるとされています。
また同グループの東武バス日光では2025年8月より日光市内の路線において、廃棄された食用油由来の環境負荷の少ないバイオ燃料を利用したバスの運行を開始しています。
新幹線移動によるカーボンオフセット「GreenEX」がスタート
2024年4月、JRグループは再生可能エネルギーの活用によりビジネスでの新幹線移動によるCO2の排出量をオフセットできるサービス「GreenEX」を開始しました。
「GreenEX」の対象となっているのは2025年8月現在、東海道・山陽新幹線(東京〜博多)と九州新幹線(博多〜鹿児島中央)の全区間。
乗車運賃と同じように区間ごとにオフセットできるCO2排出量は細かく決められており、例えば東京・名古屋間では5.7kg、東京・新大阪間では8.7kgとなっています。
いちはやくサービスの利用をはじめたアストラゼネカを筆頭に、オリックスや第一三共などの企業で「GreenEX」によるカーボンオフセットが行われています。
宮崎県庁、カーボンオフセット都市ガスを導入
宮崎県は2025年4月、県庁舎と県庁庭園で使われているガスに、宮崎ガスのカーボンオフセット都市ガスを導入することを発表しました。
このカーボンオフセット都市ガスは伐採跡地などへの再造林により吸収されるCO2分のクレジットを活用したもので、県施設への導入は全国初となります。
宮崎県は歴史的にスギなどの木材の国内有数の産地として栄えてきましたが、近年では林業従事者の高齢化や人口減少などにより伐採後に再造林が行われない事態が増えています。
これを受けて宮崎県は再造林率日本一の県を目標に掲げ、「グリーン成長プロジェクト」などの取り組みで県内の再造林を促進させています。
クレジット運用に関する国内の近年の事例
東京都カーボンクレジットマーケットがオープン
東京都は都内にある中小企業の脱炭素化を促進すべく、2025年3月にクレジットを容易に取引できる独自のシステム「東京都カーボンクレジットマーケット」を開設しました。
この事業は東京都が基本計画として打ち出している「2050東京戦略」の戦略20・ゼロエミッションを達成すべくはじめられたものです。
システム内ではJ-クレジットだけでなく、熱帯雨林の保護やメタンガスのガス漏れ防止対策など海外のプロジェクトに関するクレジットも購入できます。
自治体がクレジット取引システムを運用するのは全国初で、6月には都内のガス配給会社が第1号となるクレジットの取引を行いました。
カーボンオフセットを活用するメリット
「少ない負担で脱炭素化を実現できる」
2026年にGX-ETS(政府による企業向け排出権取引制度)が本格的に施行されることで、CO2の排出量に応じた罰則が規定される可能性があるといわれています。
カーボンオフセットを行うことで商品の製造や販売に支障を出さず、少ない負担でCO2の実質排出量をおさえることができます。
「地域社会の活性化や復興支援につながる」
J-クレジットには地方の企業や自治体のプロジェクトに関するものも多く、クレジットの購入で地域社会の活性化や被災地の復興を支援することができます。
また地域によっては地元のクレジットを活用できるよう、県などがマッチングサービスをおこなっているところもあります。
「実際にESG経営に取り組む姿勢を見せられる」
SDGsの広がりとともに環境や社会に配慮するESG経営に取り組む企業が増えた一方、グリーンウォッシングのように上辺だけ配慮している姿勢を見せている企業に対する反発も強まっています。
カーボンオフセットで具体的な取り組みを行うことで、見せかけではなく実際に環境や地域社会の保全を支援している企業であるとアピールできます。
カーボンオフセットは印刷の発注でも利用できる
会社案内や商品カタログといった冊子の印刷を発注する際にも、カーボンオフセットを活用できる印刷会社を選んで脱炭素化の活動を支援することができます。
カーボンオフセット制度を活用してつくられた印刷物には、その証として以下のカーボンオフセットバタフライロゴを記載できるようになります。

現在、数多くの自治体や企業でカーボンオフセットの取り組みが行われており、脱炭素化を実現させるためのユニークな事例もたくさん見受けられます。
負担をおさえて環境や社会にやさしい企業として持続可能性に貢献できるカーボンオフセット、より詳しく知りたい方は無料でDLできる資料もご覧ください。
・関連資料のダウンロード
 | カーボンオフセット価格表 カーボンオフセットをおこなった印刷にはいくらかかるのか価格の目安をまとめました。 |