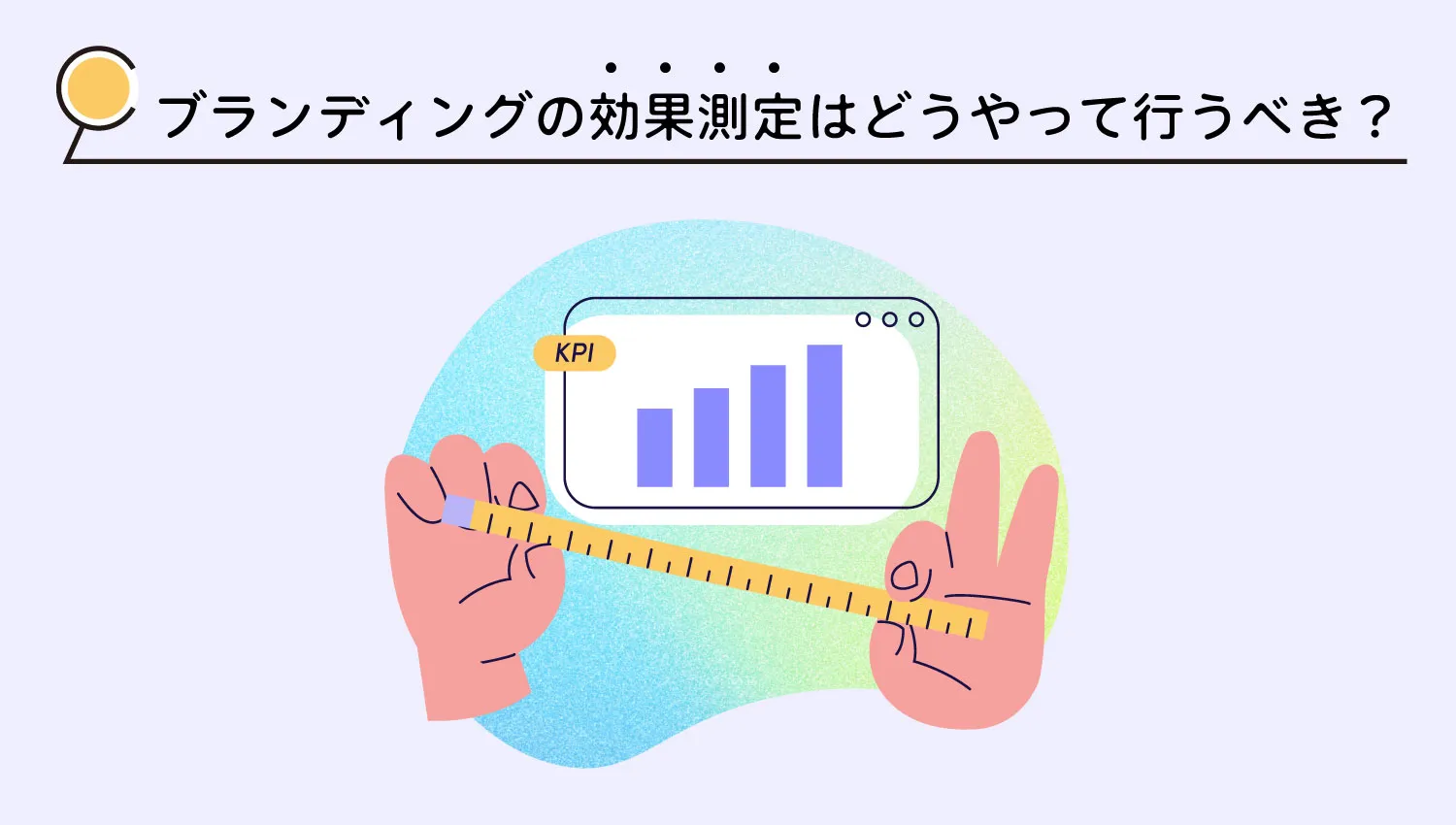ブランディングは企業の知名度を広めたり他社との違いをわかるようにしながらイメージを高めたりして、新規顧客の獲得や安定した利益の確保につなげるための重要な戦略です。
そのためブランディングの施策には、直接目に見えないものの顧客をひきつけるための効果を期待できます。
一方で結果の不可視性からブランディングは効果測定が難しく、この理由からきちんとしたブランディング戦略をたてていない企業も少なくありません。
今回はブランディングの効果測定が難しいといわれる理由から、どのようなかたちで測定すればいいか見ていきます。
ブランディングが効果測定しにくいといわれる主な理由
今回は以下の4つの理由から、うまく効果を測定するための方法を見ていきます。
① 「ブランディングによる売上・利益への影響が把握しにくい」
ブランディング施策は商品の直接的なPRというよりもブランドの知名度やイメージの向上などが目的となるため、売り上げが変動してもブランディング施策による影響があるかどうかが判断しにくいです。
実際に商品の名前自体は知っていても、買ったことや使ったことはないものは少なくないかと思います。
したがってブランディングの施策により知名度が上がっても、購入数や契約数などの数値が上がらなければ成果が出ているとはいえません。
少なくともブランドの認知度やイメージの変化が売上の増減と比例しているといった視覚的に分かりやすい情報が効果測定に必要といえます。
売上・利益へのブランディング効果を測定するための方法
「ブランドの検索数と売上の推移の相関分析」
ネットでのブランド名や商品名の検索数を計測して、同時期の売上などの推移と比較することで相関関係を分析します。
検索数が増えていることはそれだけブランドに興味を持つ人が増えたといえるため、購入理由にブランドの存在感が影響してるか把握できます。
「認知度調査と地域・店舗の売上データの照合」
地域や世代ごとにブランドに対するアンケートを行い、同じく地域や世代などの売上データと照らし合わせることで相関関係を分析します。
特にブランドや商品に初めて接触する顧客の割合(新規接触率)が高いほど、ブランドの知名度も上がっているといえ、ブランディングの効果が出ているといえるでしょう。
② 「ブランディングの効果が出るまでに時間が長くかかる」
プロモーション活動に比べてブランディング施策ははっきりと効果が出るまで時間がかかりやすく、数年かかって効果がみられるようになることも少なくありません。
「ここは〇〇のイメージがある」という会社には、長年テレビやネットなどで広告を見てきてその印象がブランドイメージにつながったところも多いかと思います。
マーケティングやプロモーションに比べてブランディングはすぐに効果が出ないため、投資などの上層部の支援や協力を得られにくい傾向があります。
ブランディング施策を「成功」させるためには、効果が時間をかけて少しずつでも出ていれば、データを長期間収集して効果測定することが重要といえます。
長期的なブランディング効果を測定するための方法
「目的に応じたKPIの定点観測」
ブランド認知度やNPS(ネットプロモータースコア)などブランディングの目的にあわせた指標を3か月ごとや半年ごとなど定期的に見て、数値の増減を比較します。
NPSは顧客にブランドを周囲におすすめする可能性があるか10点満点で評価してもらい、9点以上の推奨者の割合から6点以下の批判者の割合を引いたスコアの数値で、ブランドロイヤリティをはかる基準として用いられます。
認知度や信頼度が上がった効果を定量化しやすいため、経営層などに示せるKPIとして活用できます。
「特定のユーザーへの定期的なパネル型アンケートの実施」
同じユーザーに対して、定期的にブランドの印象や認知度などを繰り返しパネル調査を行い、イメージの変化を可視化していきます。
ブランドイメージがどう変わったか、どれほど浸透したかといったことが動きで見れるため、CMなどの効果を長期的に見て評価するのに向いています。
また同じ対象者に繰り返し調査することで、対象者の信頼感やエンゲージメントの構築にもつながり、より精度の高い回答を収集できる可能性もあがります。
③ 「ブランディングで扱う情報がデータとして定量化しにくい」
ブランディング施策は企業や商品に対するイメージや価値観など抽象的な情報を扱うため、効果測定で何を測ればよいか基準が定まりにくいです。
例えば売上高なら何円、来客数なら何人と数値をはっきり出せますが、ブランディングだと顧客が好感度や信頼度を持っていてもそのまま客観的な数値に出せるわけではありません。
そのためブランディングの効果が出ているかどうか第三者が認知しづらく、社内関係者にマーケティング施策の業績が正しく伝わりづらくなります。
ブランドイメージに関する顧客のリアルな声を、客観的に認識しやすいかたちにまとめあげて効果測定を行うことが重要となります。
抽象的なブランディング効果を測定するための方法
「ブランドイメージマップを目的としたアンケート調査」
顧客にアンケート調査を実施する際、ブランドに対するイメージを「おしゃれ」「伝統的」「安っぽい」など様々なキーワードを選んで評価してもらいます。
5段階評価などスコアとしてまとめることで顧客のイメージをマッピングできるようになり、世間で認識されているブランドの立ち位置などを把握しやすいです。
「WEB上の投稿に対するソーシャルリスニング分析」
SNSやレビューサイトなどでの自社ブランドに対する投稿を調査して、感情的な評価や頻出するワードなどを分析します。
顧客のリアルな本音を抽出できるため、企業が思う理想像と実際のブランドイメージのギャップを明確化しやすいのが特徴です。
④ 「ブランディングを行うチャネルが多岐に分かれている」
ブランディングは屋外看板、テレビCM、WEB広告など様々な媒体(チャネル)で顧客にアプローチするため、媒体ごとに効果測定をおこなう必要があります。
一方で媒体ごとに計測できる情報や方法が異なるため包括的な測定がしにくく、どの媒体で効果が出ているか測定して比較するのは容易ではありません。
また「テレビCMでキャンペーンを知ったあと、屋外広告を見て近所に販売店があるのを知って購入にいたった」というように顧客の行動に複数の媒体が関わることも多く、どの媒体が顧客に影響を及ぼすか分析しにくいといえます。
そのため、顧客が購入や問い合わせを行ったきっかけがどの媒体なのか把握しながら、全体的に媒体の効果を図れるよう効果測定をする必要があります。
マルチチャネルでのブランディング効果を測定するための方法
「カスタマージャーニー分析による接点の調査」
顧客がブランドを認知してから購入するまでの行動の流れ(カスタマージャーニー)を分析して、どの媒体に接した際の印象やその後の行動パターンをマッピングします。
チャネル同士のつながりや複数のチャネルによる顧客への影響が分析できるため、どのようにチャネルを組み合わせれば相乗効果を高められるかなどを考える上での目安となります。
「チャネルごとの印象調査とブランドリフト」
顧客にアンケート調査をする際に、ブランドを知ったきっかけや印象に残った広告媒体などを質問して、チャネルごとに好感度や理解度などの項目をスコアとして取得します。
また近年ではWEB広告を中心に「ブランドリフト」と呼ばれる調査方法も使われており、これはブランディングを目的とした広告を見たことがあるか質問し、あると答えた人にブランドに対する認知度や関心などを確認する方法です。
Youtubeなどで「次のサービスのうち、知っているものはどれですか?」といった簡単なアンケートがよく表示されますが、これもブランドリフトの一種です。
ブランディング施策の効果測定は決して難しない
企業にとって顧客の創出にかかせないブランディング施策ですが、結果がすぐに出にくい点や具体的な数値として施策の効果を表しにくい点などから、効果測定がしにくいといわれています。
しかし顧客の何をどう調べるか、調べる方法や対象を工夫すればブランディング効果を数値として表して収益などのデータと照合したり比較したりできます。
顧客からより自然な意見を集めてスコアなどで表現すれば、数値化しづらい感情的な内容も効率よく統計・分析できるようになりますよ。