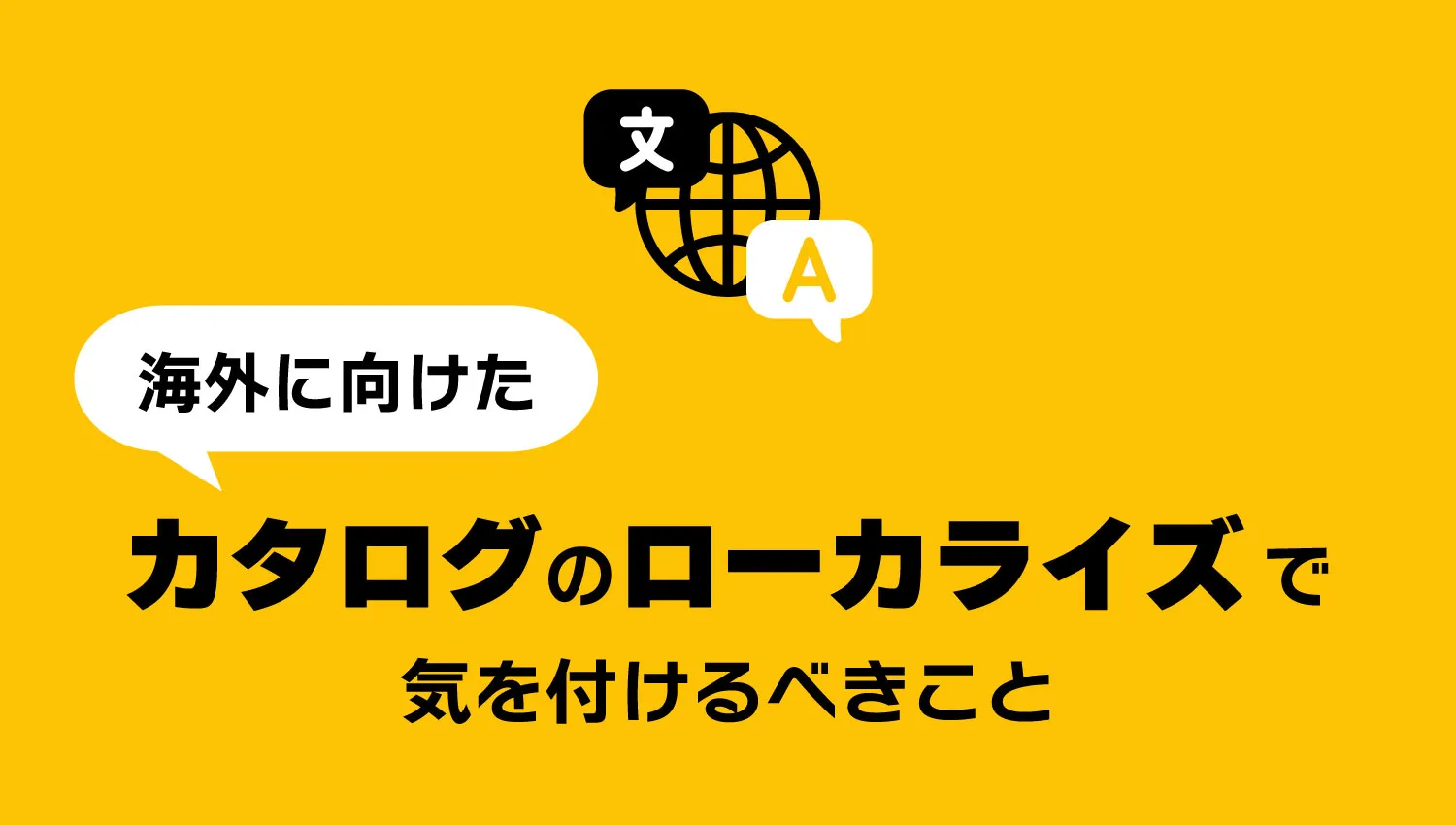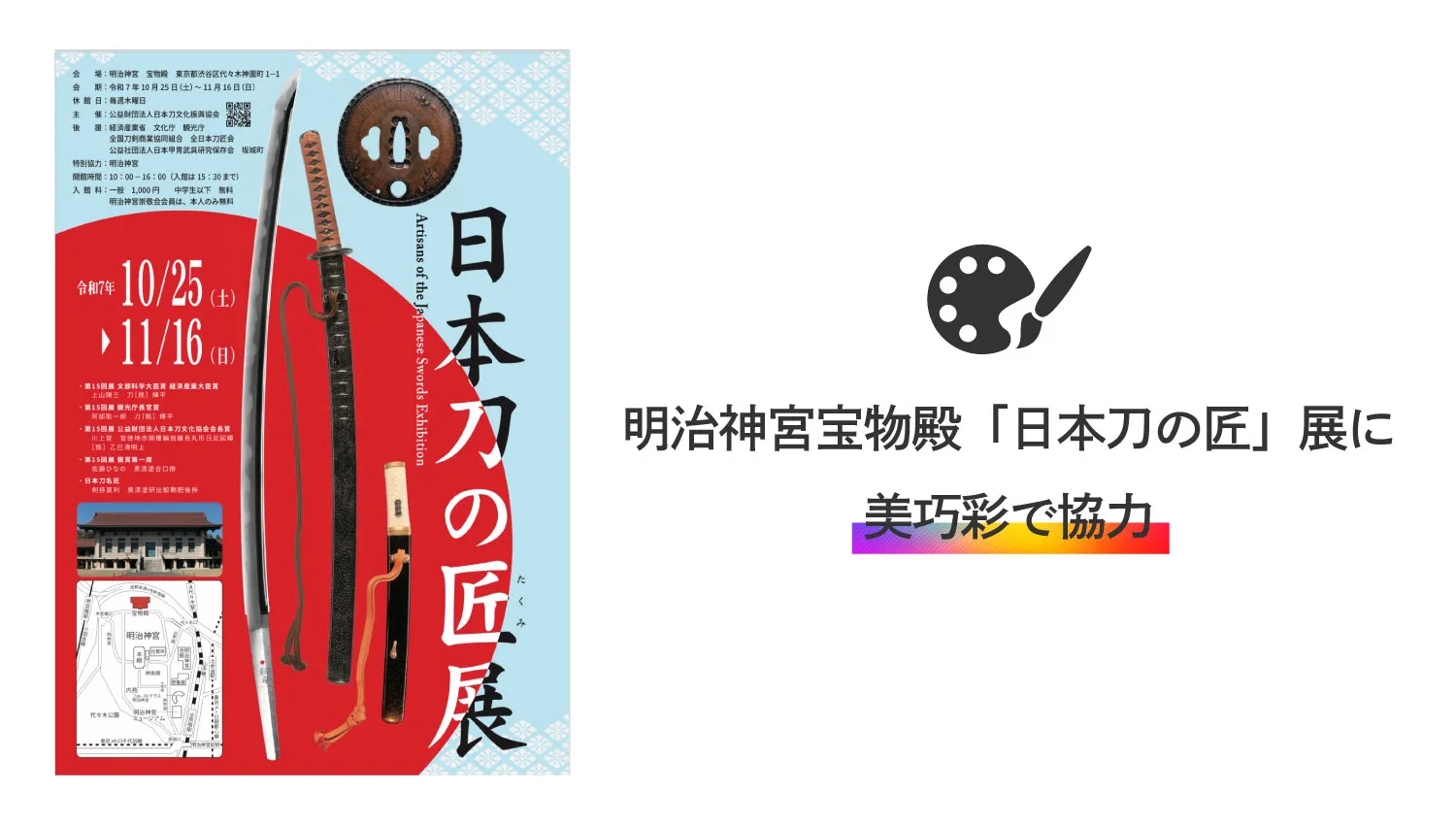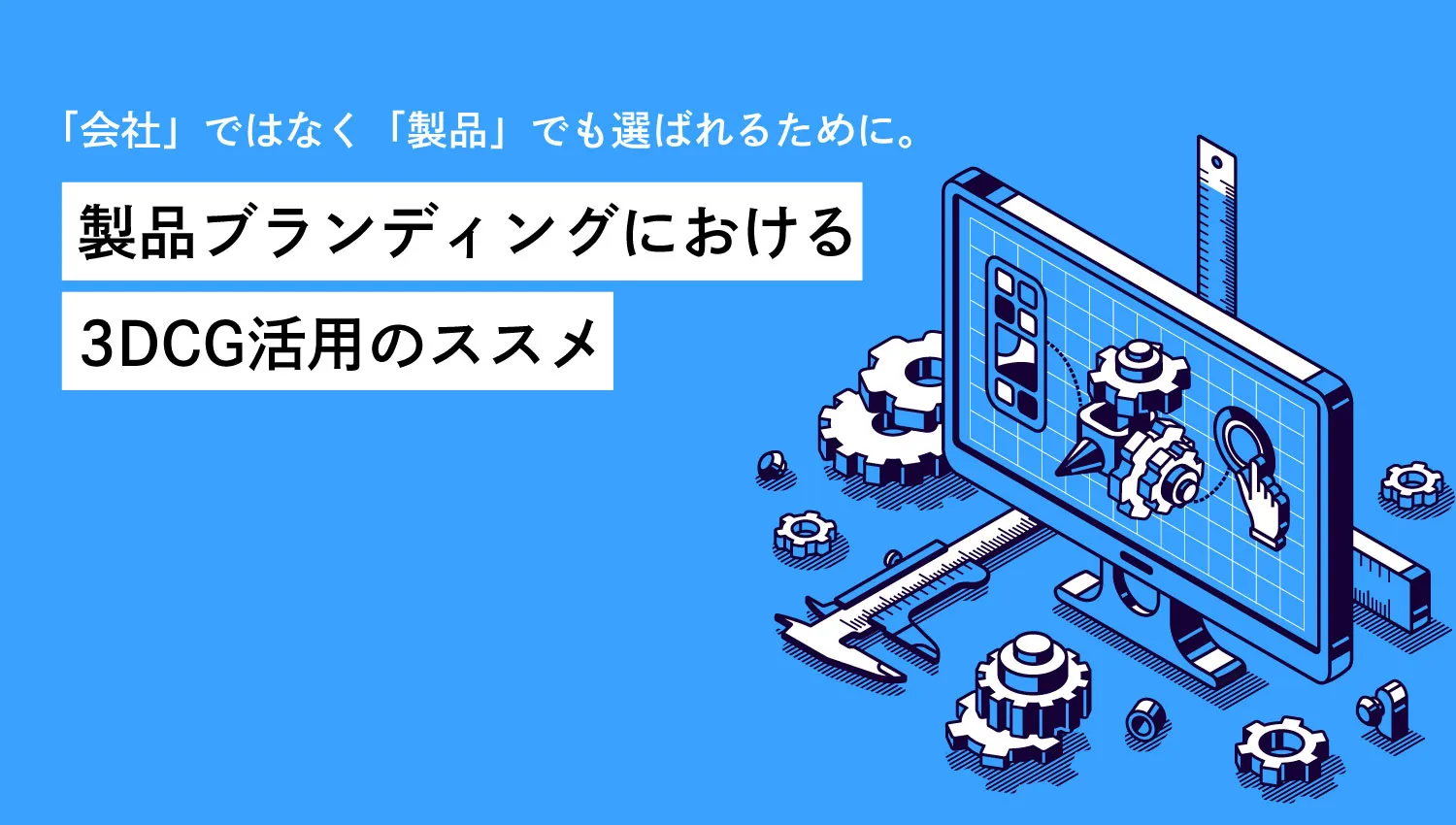人口増加率や経済成長率などの点などから、海外進出による新たな市場開拓は様々な業種にとって生き残りのための重要戦略のひとつとなりました。
しかし言葉も習慣も違う地域に自社の技術やサービスを売り込むためには、当然ながら日本国内とは違うアプローチを図ってリード創出につなげる必要があります。
特に製造業にとっては商品のカタログなどのローカライズをしっかり行わないと、どれだけ機能や品質に優れた商品であっても現地の人の関心を集めるのは困難です。
今回は自社をリードに売り込むためのカタログについて、ローカライズのポイントや成功例を紹介いたします。
「ローカライズ」は海外進出にとって必須不可欠
国内向けの製品やサービスを海外に展開する際は、表示や説明書きなどを一通り英語や中国語など現地の言葉に訳す工程が発生します。
ローカライズは単にテキストを機械的に翻訳するのでなく、現地の人が理解しやすく違和感や不快感を与えないような表現のかたちに置き換えて伝えるための作業といえます。
現地のことをしっかりリサーチしながら表現を考えていくため、作業負担がかかってしまいますがその分、確固としたブランドイメージを現地で構築しやすくなります。
日本の卵文化に着目して月見バーガーを考案したマクドナルドや都道府県ごとにご当地メニューを販売するキャンペーンを行ったスターバックスなど、日本人の習慣や地域性を取り入れた取り組みにより「日本人になじみ深い企業」として認知されるようになった事例も少なくありません。
商品カタログなどのローカライズもまた、日本のメーカーが現地の人たちになじみ深い企業として認められるための基礎的な施策といえるのです。
誤訳やニュアンスの違いで思わぬ印象を与えることも
反対に本国で展開しているキャッチコピーを機械的に翻訳して用いたところ、誤訳やニュアンスの違いから思わぬ印象を与えてしまうケースもあります。
例えば1987年にアメリカのある航空会社が自社の機体に革張りのシートを導入した際、「Fly in leather(革張りで飛ぼう)」というキャッチフレーズを採用しました。
しかしスペイン語圏向けに広告を展開した際、キャッチフレーズを直訳した「Vuela en cuero」がメキシコでは「裸になって飛ぼう」というニュアンスとなってしまい、シートの良さが伝わらない広告となってしまいました。
また2018年にはイタリアを代表するファッションブランドが中国でイベントを開催した際、その宣伝動画の描写が差別的であるとして大きな騒動になったこともあり、海外進出の成功においてローカライズによる現地の人に配慮したアプローチは必須不可欠だといえます。
カタログをローカライズする際に気を付けるべき6つのこと
ここからはメーカーの製品カタログを、海外市場向けにローカライズする際に気を付けるべき6つのポイントを紹介します。
① ローカライズを行うターゲットをはっきりさせる
海外市場と一言でいっても、国や地域によってマーケットシェアの現状やリード顧客の行動パターンが異なってきます。
例えば購買にいたるプロセスを見ると、日本人は品質やコストパフォーマンスを比較しながら決める人が多く、アメリカ人は価格や機能などでお得に感じたら即決で購入する人が多く、中国人はネットなどで評判を念入りにチェックして慎重に判断して購入する人が多いといわれています。
どこの国や地域に向けてカタログを展開するかによって、どのような内容にしたら現地の人にアプローチしやすいか変わってきます。
その結果、カタログをローカライズするために変えるべきところもおのずと見えてきやすくなります。
どの国や地域にどんな目的で市場開拓を行い、そのためにはカタログでどのような情報を発信すべきか事前にじっくり検討しておきましょう。
② 現地の人に「しっかり伝わる表現」をこころがける
ローカライズに求められるのは単なる翻訳ではなく、現地の人が製品や企業を知ってもらえるようよりこちらの意図が伝わりやすい表現に訳すことです。
そのためには現地の人が実際に使う言い回しやニュアンスなどもまぜながら訳す「トランスクリエーション」の考えが重要になります。
例えば人気ゲームシリーズのファイナルファンタジーXVIが海外向けにリリースされた際、キャラクターのセリフを単に英訳するのではなく、実際の英語の方言を導入して彼らの個性を際立たせるようにしています。
カタログのキャッチコピーや説明文は見ている人に製品の良さを知って関心を高めるために記載されるものですが、そのためには「しっくりくる表現」で伝えることが重要です。
機械翻訳だけではなく、国・地域やカタログを見てもらうターゲットのペルソナなどにあわせてできるだけ状況に適した表現で訳すようにしましょう。
③ その土地の価値観や倫理観に反しない表現を用いる
海外の国々は日本とは文化や風習が大きく違うため、カタログの内容に現地の人が不快に感じない表現を心がけることも重要です。
文章の言い回しはもちろん、挿絵で入れたイラストのジェスチャーや服装といったところまで細かく見ておかないといけません。
例えば日本ではOKサインのジェスチャーが表示されていても特に問題はありませんが、ブラジルでは相手を侮辱するニュアンスがあったり、中東では呪いや脅迫のポーズとして認知されていたりするため、国によって利用が適さないこともあります。
ほかにもペプシコーラが自社で使っていた「Come alive with Pepsi(ペプシで生き生きと)」というスローガンを中国語圏に向けて翻訳した際、「ペプシで亡くなった先祖を蘇られる」と誤訳されてしまい、現地の人の宗教的倫理観に反する内容となってしまったという例もあります。
このような何気なく訳した結果がとんでもない誤訳を招いてしまうことは意外とよく見られるため、後述する現地の人による最終チェックなどが重要になってきます。
④ 現地のユーザーが認識しやすいデザインに調節する
日本語の文章を基にしてカタログのレイアウトを設計していたが、翻訳した外国語の文章を原稿に入れてみるとテキスト量が変わってしまい、結果非常にアンバランスなレイアウトになってしまったということも少なくありません。
例えば「蛍光灯」という日本語を英訳すると「Fluorescent lamp」と比較的長い文字列に変わってしまうため、翻訳結果を図表に記載しようとしたら窮屈な見た目になってしまう可能性があります。
一般的に英語の文章の文字数は、同じ内容の日本語の文章の1.5倍から2倍になるといわれていることからも、英訳した内容をそのまま掲載することでレイアウトの崩れが起こりやすくなることがうかがえます。
日本の雑誌やWEBサイトは外国のものに比べて、一目で認知できる文字情報量が多いといわれています。
カタログのレイアウトが崩れないよう、文章量を調節しながら掲載するのもローカライズのポイントです。
⑤ 現地スタッフによるネイティブチェックを実施する
機械翻訳の技術はこの数十年で大きく進化しましたが、まだ100%完璧な表現に翻訳できるわけではありません。
そのため誤訳や適切でない表現が翻訳結果に含まれていないか、カタログを展開する前に内容を現地の人に必ずチェックしてもらうようにしてください。
また国によって著作物の権利や広告規制に対する法令なども変わってくるため、念のために弁護士などの専門家にチェックしてもらうのも大事です。
⑥ デジタルカタログを展開する場合に気を付けるべきこと
PDFやアプリなどでデジタルカタログをローカライズする場合は、紙のカタログ以上に気を付けるべきことが増えてきます。
例えばデジタルカタログは公開した後も、最新の企業情報や製品の製造状況などをリアルタイムで更新していく作業が発生します。
テキストを翻訳したり現地の方にチェックしたりする手間がかかる分、修正したファイルのアップロードなど他の工程を効率化させてスムーズに更新できるようにしておくことが重要です。
WEBサイトをローカライズさせている日本の企業事例
海外進出している日本企業の中には、日本版と海外版で公式サイトの構成やレイアウトを変えているところも少なくありません。
今回はそんな企業の事例を3つ紹介します。
日本企業の事例その①:トヨタ自動車
トヨタ自動車は世界的な自動車メーカーとして世界各国に現地法人を展開しており、それぞれの公式サイトでレイアウトは大きく違っています。
例えば日本版公式サイトのトップページはアクアやGRヤリスといった定番商品の写真を並べたカタログ形式のレイアウトがメインとなっています。
一方、アメリカ版公式サイトはカタログとしての要素もありつつ、ランドクルーザーなどの車種が夜の街を走っている動画を入れるなどビジュアル面のインパクトを重視したレイアウトとなっています。
フランス版やドイツ版の公式サイトではトップページのメニューバーに「電気自動車」の項目があり、環境意識の高い地域性を反映したレイアウトとなっています。
日本企業の事例その②:吉野家
吉野家は日本を代表する牛丼チェーンとして、複数の国と地域に店舗を持っています。
日本版の公式サイトではトップページの項目が「メニュー」の次に「店舗検索」「テイクアウト予約」という順番になっており、誰もが知るブランドだからこそトップページからすぐ店を調べたり出前を頼んだりとスムーズに商品にたどりつくようなレイアウトとなっています。
一方、米国版の公式サイトでは「メニュー」の次に「企業情報」の項目があり、そのページから会社としての歴史やいきさつを知ることができ、現地の人にまず吉野家のブランドを知ってもらおうというような狙いが見えてきそうです。
ほかにも買い物のポイントを利用する人の多い国民性から、「店舗紹介」よりもポイントを貯められる公式アプリの項目が優先されているのも、土地柄が反映されているといえますね。
日本企業の事例その③:パナソニック
様々な種類のエレクトロニクス製品を製造しているパナソニックの場合、国によって売れ筋となる商品が変わるためWEBサイトのレイアウトもその影響を受けています。
日本版公式サイトは、炊飯器や洗濯機など白物家電のカテゴリーが商品情報の一番上に表示されていて、トップページにも調理に関する情報を紹介する記事へのリンクが掲載されています。
一方イギリス版公式サイトではテレビやデジタルカメラなどの項目が商品情報で前に来ており、トップページでは企業のサステナビリティ情報に関するリンクが見られます。
他にもインド版ではエアコンが、ブラジル版ではドライヤーが前に来ており、国ごとに人気のあるジャンルの商品を中心としたレイアウトを意識したつくりになっていることがわかります。
現地の事情や背景をきちんと考慮した「ローカライズ」を
メーカーが海外マーケットに進出しようとする際、カタログを単に翻訳するのではなく現地の人にとって違和感や不快感のない表現に置き換えて伝えるローカライズが重要になります。
カタログにローカライズで重要なのは、どんなターゲットに向けた内容にするかしっかり決めて、ニュアンスによって誤った意味に解釈されないようにトランスクリエーションをして、現地の価値観に反しない内容や翻訳による文章の変容を考慮したデザインを取り入れることが必要不可欠です。