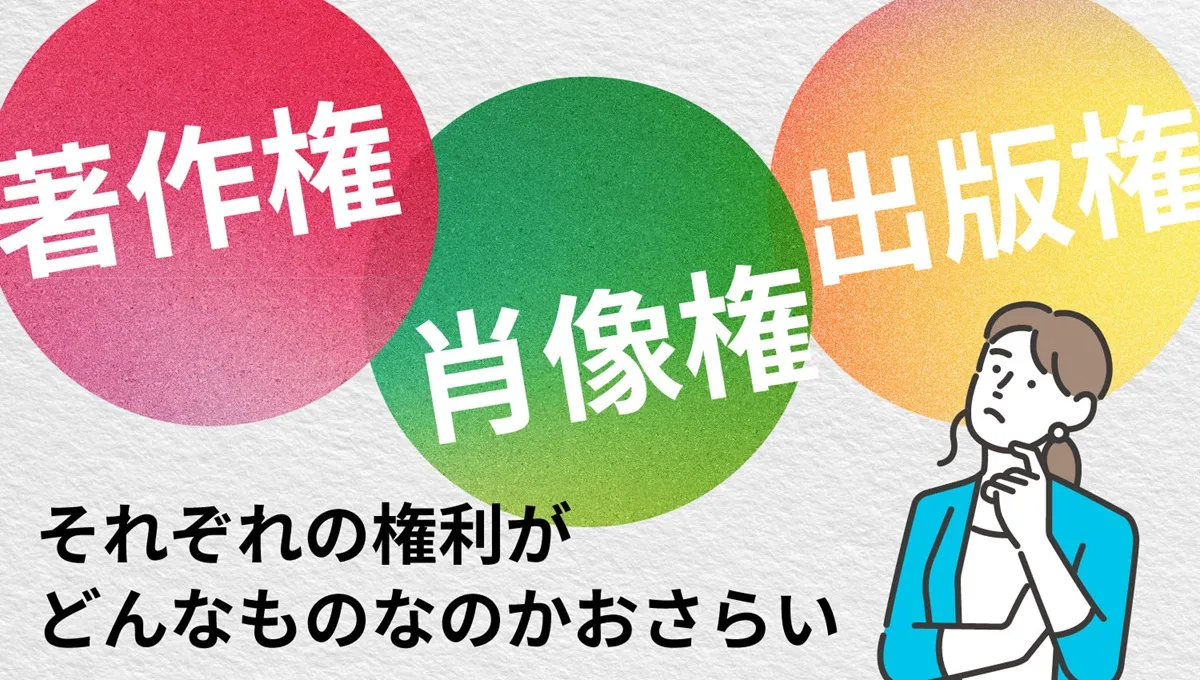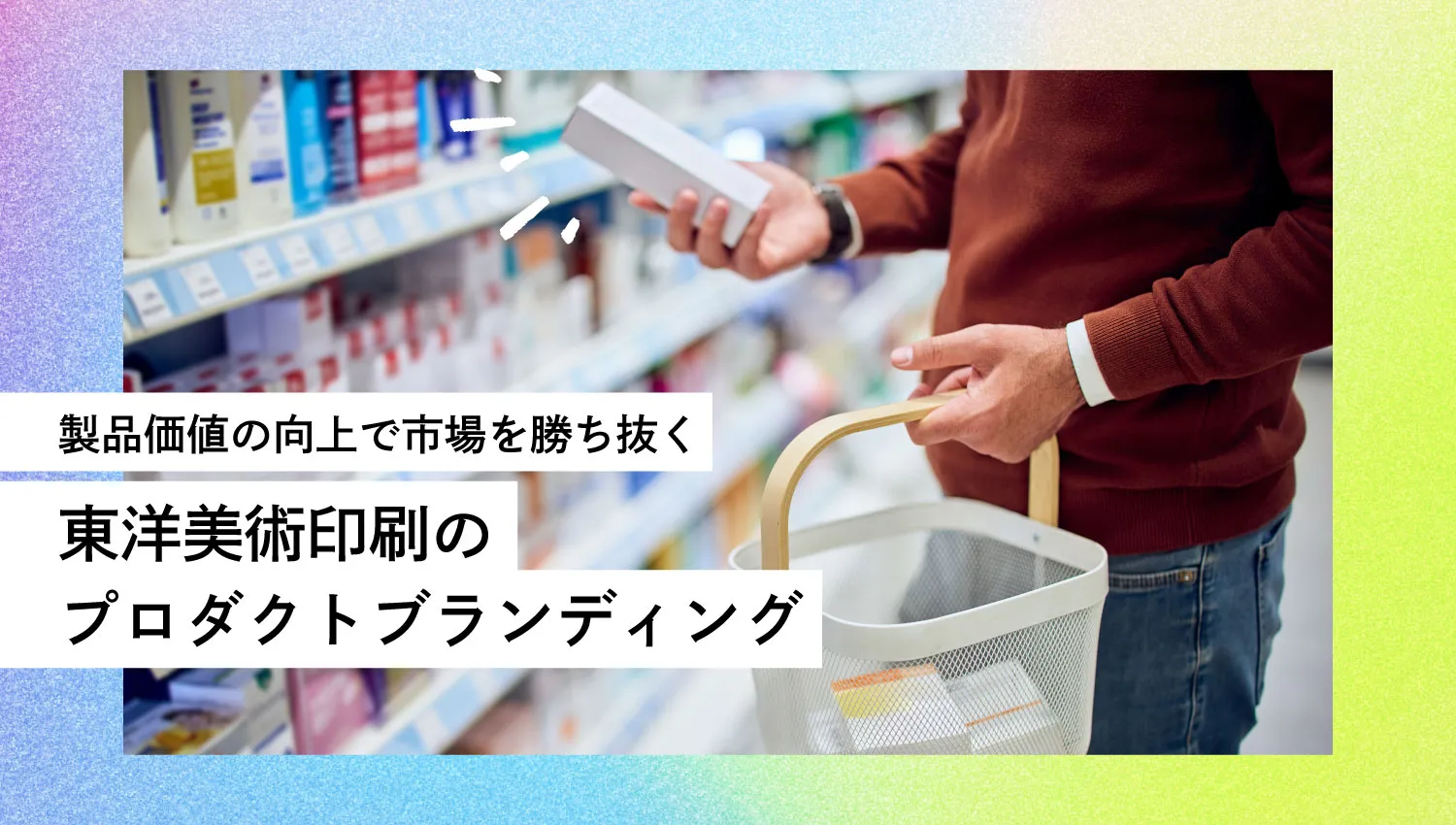著作権や肖像権といった言葉を普段からニュースなどでよく目にしますが、何に対する権利でどの範囲まで適応されるのか細かくまではよく分からないもの。
特にSNSに投稿した画像やAIで生成した画像など、WEBやデジタルに関するものにはどう権利が関わってくるのか気になる方も少なくないのではないでしょうか。
普段ニュースなどで耳にすることも多い著作権を筆頭に、IPと呼ばれる知的財産権の種類として肖像権や出版権など様々な権利があげられます。
そこで今回は、代表的なIPである著作権・肖像権・出版権がそれぞれどのような権利なのか見ていきたいと思います。
「著作権」…自分の作ったものを保護して自由に扱うための権利
著作権は文章、絵画、楽曲といった著作物をどのように扱うかを、その作者である著作者が自由に決めることができる権利です。
一般的に著作権の保護期間は著作者の死後70年までで、著作者が複数名いる場合は一番最後まで生存した著作者の死後70年の保護期間とします。
著作権には「著作人格権」と「著作財産権」の2種類に大きく分けられますが、どちらも権限を譲渡したりしない限り権利は著作者のものとなります。
著作権に分類される2つの権利:「著作人格権」
「著作人格権」は著作者の意思や主張などを表現するために与えられる権利で、主に以下の種類があります。
公表権
著作者が著作物をいつどのように公開するか自由に選択できる権利です。
例えば著作者がある作品の公表を望んでいない場合、外部の人間が無断で公開するのは公表権に反する違法行為となります。
過去にはある週刊誌が映画の脚本の一部を無断で引用していたことが、公表権を侵害しているとして有罪になったケースもあります。
氏名表示権
著作者が著作物に自身の氏名を表記するかどうか、あるいは本名やペンネームなどどんな形で表記するかを決められる権利です。
例えば作者の個人名を表示しないで有名なイラストレーターの作品をSNS上に無断で投稿すると氏名表示権の侵害とみなされる可能性が高いです。
一方で著作物の製作者を誤解してしまうおそれがなければ氏名表示の省略が認められており、例えば施設内でBGMとして楽曲を流す場合にはその作詞者・作曲者を必ずしも表示する必要はありません。
同一性保持権
著作者の許可なく著作物の内容を変更、改変されないようにするための権利です。
例えば小説作品をドラマ化する際に本人の許可なく脚本を原作から大幅に変更するのは同一性保持権違反とみなされます。
ただし難解な漢字をひらがなに直すといったやむをえない改変や、ソフトウェアのバグやエラーを修正して利便性をあげるための改変などの例外は認められています。
著作人格権にはこの他にも、著作者の意思で著作物の複製や販売の中止を請求できる「出版権廃絶請求権」などの権利があります。
著作権に分類される2つの権利:「著作財産権」
「著作財産権」は著作物により著作者が正当な利益や評価を得るため、第三者が著作物の販売や複製などの行為を許可する権利で、主に以下の種類のものがあります。
複製権
著作物を印刷や録音やスキャン作業などにより複製する権利です。
著作者に許可なく書籍や楽曲のファイル、ソフトウェアをネットにアップロードして共有する行為は複製権侵害とみなされ、違法となります。
ただし正規の手段で入手した著作物を個人で私的に複製する場合は、例外的に権利が認められています。
上演権・演奏権・上映権
著作物を公共の場で自由に上演・演奏・上映する権利です。
たとえばコピーバンドが有名なミュージシャンのカバーアルバムを販売する場合、楽曲の作曲者・作詞者から演奏権の許諾を得る必要があります。
また映画館で無断に作品の映像を撮影してネット上に投稿するといった行為は、上映権の侵害となり厳しく罰せられます。
公衆送信権・公衆伝達権
公衆送信権はインターネットや民間放送などに著作物を送信する権利で、公衆伝達権は公衆送信された著作物をテレビやスクリーンなどを使って公衆に共有する権利です。
例えば漫画家や写真家などが自分の作品をSNSに投稿するのは公衆送信権で認められた行為であり、当人以外が自分の著作物として無断で公開できないようになっています。
一方で直接的な営利目的ではない著作物の放映と認められた場合は著作者の承諾が不要となり、例えば飲食店や待合室の家庭用テレビで番組を流すのは法律的には何の問題もありません。
譲渡権
複製した著作物を公衆に頒布・販売(譲渡)できる権利です。
書店やレコードショップで正規に複製された書籍やCDを販売する行為が該当し、いわゆる海賊版や違法コピーを販売するのは譲渡権の侵害となります。
一度頒布・販売された時点でこの権利は消失するため、読み終わった書籍を古本屋やフリーマーケットで売る行為は譲渡権に違反した行為にはなりません。
貸与権
著作物を有料でレンタルする際に発生する権利で、レンタルショップで映像作品や漫画などを有料で貸し出すには著作者の許諾が必要になります。
ただし図書館や資料館などは基本無償であることや社会教育を目的とした公共性の高い施設であることから、例外的に無償での著作物の貸し出しが認められています。
二次的著作物の利用権
二次的著作物とは著作物をもとに内容や表現形態を変えながらつくられた創作物で、文学作品の英訳版やヒット歌謡曲のアレンジ曲、ファンによる同人作品などがあてはまります。
同人作品に関しては原作者が起訴すれば著作権侵害となるものの、愛好家の増加による経済効果の高さや若手作家を発掘できる可能性から、版権を持つ出版社は基本的に黙認しているグレーゾーンとなっています。
AIを生成してつくられた「創作物」の著作権について
著作権の対象となるのは著作者の思想や観念を創作的に表現したものとされ、生成AIによってつくられた創作物には著作権は発生しません。
またイラストの画風や楽曲の作風までは著作権の対象とはならず、特定の著作物をAIに模倣させて創作物をつくることは直接的な著作権違反とはなりません。
一方で既存の著作物と内容の類似性が見られる場合は著作権侵害となり、「〇〇の作品っぽい」まではセーフですが「〇〇の作品と同じ部分が見られる」というのはアウトになります。
例えば2025年8月、読売新聞社が生成AIの回答結果に新聞記事の文章や画像が無断で複製されているとして、AIによる検索サービスを展開するアメリカのパープレキシティ社に対して裁判を起こしています。
また中国では生成AIで実際のウルトラマンの画像を自由に複製できてしまうとして、円谷プロから独占著作使用権を得ている中国企業が、AIの運用会社を訴えて裁判により損害賠償が請求される事件が発生しています。
著作権と「商業財産権」の大まかな違い
著作権と似たような権利として、市販されている商品やサービスの機能やデザインに関して製作者に与えられる「商業財産権」というものがあります。
商業財産権には商品やブランドなどの名前に発生する「商標権」や商品のデザインや機能などに発生する「意匠権」などがあります。
実際にはゲームのキャラクターやロゴのデザインは商業財産権、使用している楽曲や画像は著作権が発生するというように、ある著作物に商業財産権と著作権が両方発生することも多いです。
「肖像権」…自分の容姿を勝手に公開されないようにする権利
肖像権は自分の顔や姿(肖像)を勝手に公表されるのを防ぐ権利で、大まかに「プライバシー権」と「パブリシティ権」に分けられます。
肖像権に分類される2つの権利:「プライバシー権」
「プライバシー権」は本来本人の氏名や住所などの個人情報を許可なく公にしないための権利で、肖像権のプライバシー権は本人の容姿を個人情報の一種として保護しています。
公共の場所で撮影を行う場合は不特定多数の人の顔が映りこんでしまうため、プライバシー権の観点からぼかしなど個人を特定できなくする工夫が必要となります。
しかしネットやSNSの爆発的な普及とともに世界中の人々が絶えず情報を発信するようになり、プライバシー権の侵害が問題になることも多くなりました。
また芸能人や有名人であってもプライベートな領域ではプライバシー権が発生しますが、「報道の自由」や「知る自由」が優先されることも少なくありません。
肖像権に分類される2つの権利:「パブリシティ権」
「パブリシティ権」は芸能人や政治家といった有名人の個人情報が持っている経済的価値や思想的価値などを、本人の許可なく使用するのを防ぐための権利です。
例えば当人に無断で「タレントの〇〇も愛用しています」と商品を宣伝したり、画像の入ったグッズを販売したりするのはパブリシティ権に違反する行為となります。
実際に2007年には有名人が無断で写真を記事に掲載されたとして、週刊誌の出版社をパブリシティ権の侵害で告訴した事例があります。
「出版権」…自分の書いた著作物を出版・販売する許可を与える権利
出版権は小説や漫画といった出版物を出版したり頒布したりする権利を、出版社や販売店など特定の相手に与えるための権利です。
このため自費出版のように、書籍の印刷や製本だけを業者に依頼して販売は独自に行うといったこともできます。
出版権は基本的に印刷物に対する権利であり、楽曲や映像作品や公演など著作物には適応されません。
基本的に出版権の有効期間は原則的に最後に著作物が出版されてからの3年間です。
出版権による出版社に与えられた「権利」と「義務」
出版権は著作者と書面での契約をむすぶことで、出版社側に与えられる権利です。
出版社は契約により自社以外の企業や個人が勝手に書籍を出版しないよう禁ずることができます。
ただし実際に第三者による出版を差し止めするには、文化庁に出版権を登録する必要があります。
この時、出版社が著作物使用料として著作者に支払われる金銭がいわゆる印税です。
著作権、肖像権、出版権 似ているようでそれぞれ違う
知的財産権の中でも、特に耳にすることの多い著作権、肖像権そして出版権についてみていきました。
それぞれの大まかな違いを比べてみると以下のようになります。
| 著作権 | 肖像権 | 出版権 | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 著作物 | 人物の顔・外見 | 出版物 |
| 権利者 | 著作者 | 被写体自身 | 契約を結んだ出版社 |
| 具体例 | 書籍、音楽、絵画など | 写真、動画など | 小説、漫画など |
| 概要 | 作品の取り扱いを作者が自由に決められる権利 | 個人の容姿を無断で撮影・公開されない権利 | 契約により著作物を自由に出版できる権利 |
| 保護期間 | 権利者の死後70年 | 権利者の存命中 | 最後の出版から3年 |
実際にはこのほかにも商業財産権などもかかわり、それぞれの権利は場合によってかなり複雑に関係していきます。
近年では生成AIやSNSなどにより、こうした権利に関する問題を目にすることも多くなりました。
きちんとどこまでがよくてどこからが違反なのか調べたうえで、正しく著作物と向き合うことがよりいっそう必要だといえます。