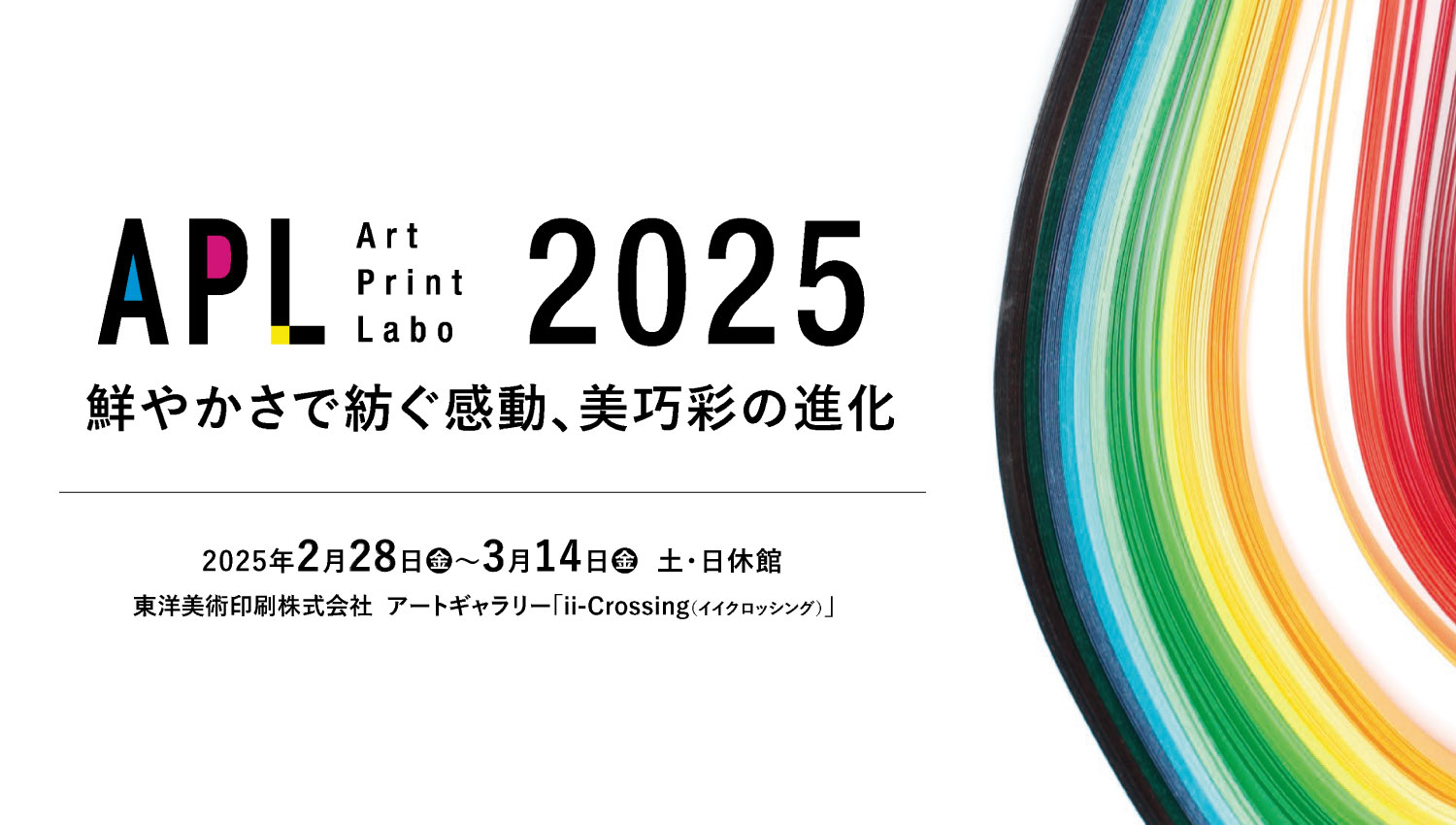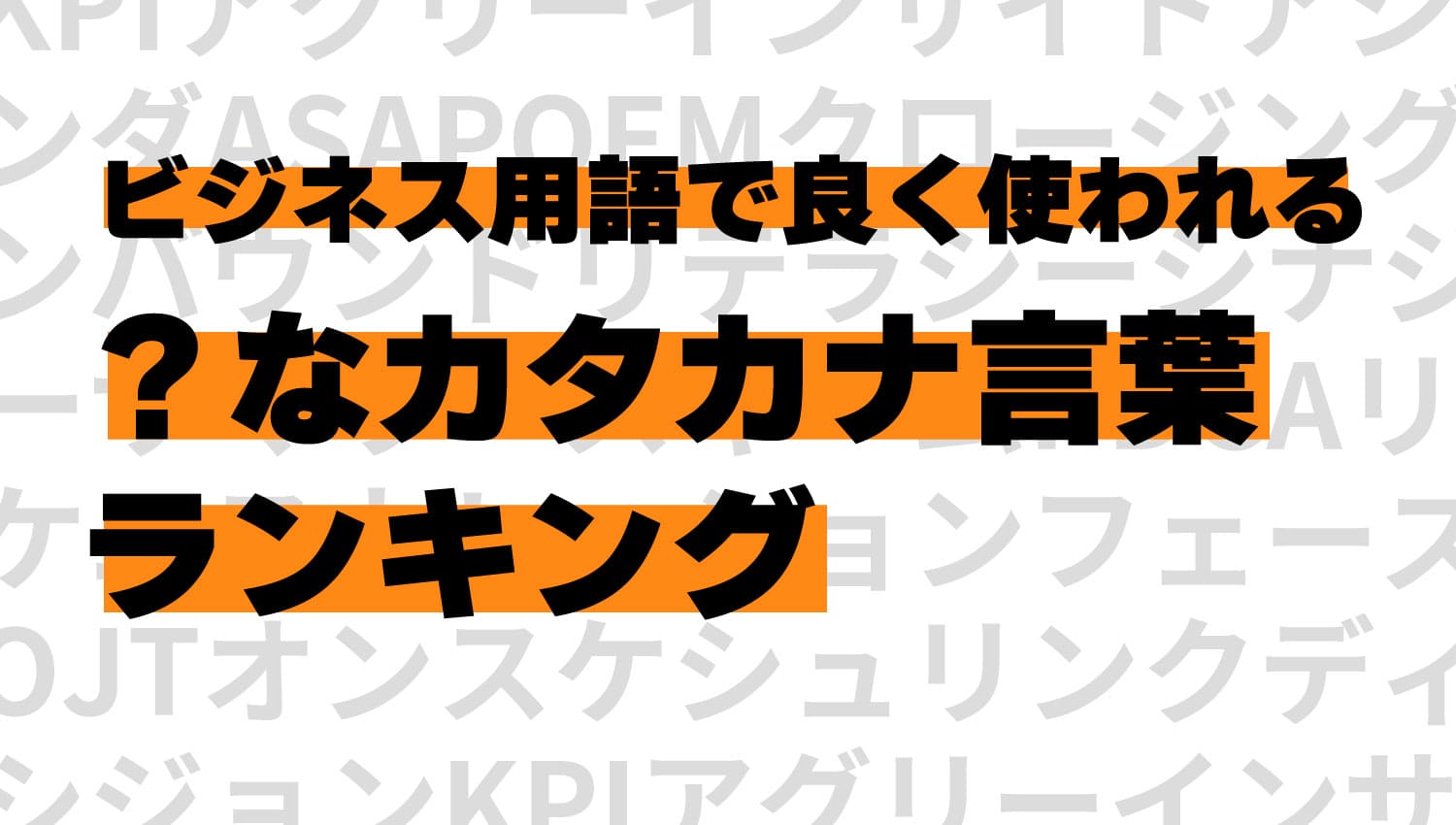近年、多くの企業や団体が「ウェルビーイング(Well-being)」の実現や向上を掲げた取り組みを行っています。
ウェルビーイングとは個人ひとりひとりや社会全体がよい(well)状態(being)であることを示す言葉です。
言葉は似ていても「健康」や「幸福」とは意味が違うウェルビーイング、今回は中でもシニア世代のものについて細かく見ていきます。
シニア世代のウェルビーイングを考えることで、今後ますます規模が大きくなるであろうシニアマーケティングに役立つ気づきがあるかもしれません。
「ウェルビーイング」が広まりだしたいきさつ
ウェルビーイングという言葉はWHO(世界保健機関)が1946年に提唱したWHO憲章において、「健康とは肉体的にも精神的にも社会的にも満たされた状態である」という文ではじめて登場しました。
これは個人の心身の容態だけでなく、人間関係や経済状況など社会的な要因も健康状態に大きく影響してくるという意味です。
近年、世界中に広まったSDGsでは3番目の目標に「Good Health and Well-Being(すべての人に健康と福祉を)」とあり、ウェルビーイングの考えは人間の健全な生活にとって重要なファクターであることがうかがえます。
日本で行政や企業がウェルビーイングに注目するようになったきっかけは、2019年以降の世界的なコロナウイルス流行による人々の生活習慣の変化といわれています。
コロナ禍で在宅ワーク導入などによるメリットを享受した高所得者層、享受していない低所得者層の間でウェルビーイングの格差が所得の格差以上に広がっていきました。
こうした背景を受けて、2021年に政府が成長戦略実行計画の中で「ウェルビーイングを実感できる社会の実現」を目標のひとつとして言及するといった動きが見られています。
今求められる「シニア世代のウェルビーイング」
国連による調べでは2015年時点ですでに日本の全人口における80歳以上の割合は約7.8%、60歳以上の割合で見ると約40.9%と、かなりのパーセンテージを占めているのが分かります。
高齢化が進んでいる日本にとって、特にシニア世代のウェルビーイングの実現は今後の社会における無視できない課題となるでしょう。
しかしシニア世代は老化による身体能力や認知能力の衰退、孤独化といった要因により幸福度が下がりやすい点から、自身の生活に対して不安感を抱きやすいです。
2018年、バイエル薬品が全国の65歳以上の方を対象に実施したアンケートの結果によると、回答者の約69%が年を取ることに対して何かしらの不安を感じると答えています。
特に不安に感じることとして「体力が衰退すること」、「要介護の状態になること」、「自立した生活が難しくなること」などがあげられていました。
また50代や60代などシニア世代より一段階下の世代も、将来の老後の生活に対する不安を強く抱いています。
朝日新聞Reライフプロジェクトが行ったアンケートでは、50代・60代を中心とした回答者の97%が健康面や経済面など老後の生活に不安を感じていると答えています。
シニア世代のウェルビーイング実現には、こうした「老後の不安」を取り除くことがとても重要となります。
「シニア世代のウェルビーイング」実現のための施策とは
ウェルビーイングは「身体的、精神的、社会的に良好な状態」という意味です。
シニア世代にとって何に注意すれば良好な状態になるのか、一つずつ見ていきましょう。
身体的に良好な状態、基礎体力が衰えず病気やケガもしない健康な体を作るためには、適度な運動習慣、栄養の整った食生活、定期的な健康診断の受診などが挙げられます。
精神的に良好な状態、ストレスなどを抑制したり脳の働きの衰えを防いだりするためには、活発なコミュニケーション、仕事や趣味などの生きがいを持つことなどが挙げられます。
社会的に良好な状態、暮らしの悩み事をなくして快適な生活を実現するためには、家事のサポート、身の回りの手続きの代行、年金などの資産や所有物の管理などが挙げられます。
近年では様々なジャンルの企業が、シニア世代のウェルビーイングにつながるような独自の製品やサービスを展開しています。
「健康面」「精神面」「生活面」でサポートする事例をいくつかご紹介します。
「シニア世代のウェルビーイング」実現に関する企業の取り組み事例
シニア世代を健康面でサポートする事例
青山学院大学理工学部は通信機器メーカーのアーチ技研と共同研究を行い、体にセンサーなどの器具を装着せずに寝るだけで心拍数や呼吸の状態を計測できる機能が備わったベッドを開発しています。
様々なデータを分析することで、高齢者など要介護者の生活リズムに異変が起きていないか瞬時に確かめられるようになっています。
四国を中心にドラッグストアなどの店舗を運営する四国メディカルサポートグループでは、高齢者の栄養摂取状況を把握して低栄養状態になるのを防ぐため、タブレットを用いた栄養ケア支援のシステムを展開しています。
IT技術により薬剤師や医師がスムーズに情報を連携することで一人ひとりに最適なアドバイスを行っています。
フィットネス施設の運営を行うパーソナルトレーナージャパンは、日本初となる中高年や高齢者を専門としたパーソナルトレーニングジム「心身健康倶楽部」を展開しています。
プロのトレーナーによる運動や食事管理のプログラムを個別で提供しているほか、YouTubeで運動習慣に関する情報の動画を配信してシニア世代の健康維持をサポートしています。
シニア世代を精神面でサポートする事例
シニア関連のデジタルマーケティングなどを行うオースタンスでは、50代以上のシニア世代向けのSNSサービス「趣味人倶楽部」を運用しています。
趣味人倶楽部は2025年2月時点で36万人の会員が利用しており、旅行やダンスなどの趣味のコミュニティや毎月開催されるイベントに参加することで会員同士で親睦を深められるようになっています。
公文教育研究会の事業部門である学習療法センターはシニア世代向けの個人向けサービス「KUMONの脳トレ」を2023年に立ち上げました。
サブスクリプション形式のこのサービスでは、毎月自宅に届くドリル教材を解いて、その結果をもとにスマホで認知機能を測定したり、ユーザー専用サイトで役立つ情報を閲覧したりできるようになっています。
温泉旅館・ホテル専門の宿泊予約サイト「ゆこゆこ」は、旅行サイトの中でも特にシニア世代からの高い評価を得ています。
ゆこゆこはシニア世代向けの旅行商品を温泉旅行に絞り込み、社員に温泉ソムリエの資格を取得させるといった独自の施策を行うことで、気軽に相談しながらプランが組めるようシニアの旅行者をサポートしています。
シニア世代を社会的にサポートする事例
みずほ信託銀行では信託商品にシニア向けの生活支援のオプションをつけられる「選べる安心信託」を提供しています。
清掃業者によるハウスクリーニングや通信会社による防犯サポートなどの優待制度を1つ無料で利用できるほか、困りごとをヒアリングして家事代行や住宅改修などの専門業者を紹介してくれるサービスも行っています。
冠婚葬祭事業を展開するサン・ライフでは、シニア世代の”終活”をワンストップでサポートする「ライフリリーフ」というサービスを提供しています。
サービスの対象は子供が別居したり配偶者が死別したりして独り身となった高齢者で、亡くなった後の葬儀・埋葬だけでなく、遺言書作成や不動産の売却手続きなども承っています。
高齢者ケアサービスを展開しているAgeWellJapanは、専任のパートナーが定期的にシニア世代の自宅に出張して生活支援を行う「もっとメイト」というサービスを提供しています。
日常会話の相手役や外出時の付き添いやオンラインでの作業の代行などシニア世代の暮らしを豊かにするよう、パートナーが様々な形でサポートしてくれるのが特徴です。
「シニアのウェルビーイング実現」のニーズは今後も大きくなる
近年経済的な豊かさでは測れない「ウェルビーイング」が多くの国で注目されていて、コロナ禍以降は日本でもウェルビーイングの実現に取り組む企業や団体が増えてきました。
中でも生活に不安を感じやすいシニア世代のウェルビーイング実現は、高齢化が進んでいる日本にとって無視できない課題となっています。
そのため国内でも近年あらゆる業種の企業や機関が、健康面や精神面などからシニア世代の暮らしをサポートするサービスや技術を手掛けています。
シニア世代にとっては白内障や緑内障などによる視覚機能の劣化も、無視できない老化による不安要素の一つです。
視力の弱い方や視覚機能にハンディキャップのある方でも安心安全に暮らせるよう、弊社では不特定多数の方が見るパッケージや看板などの情報デザインをUCD(ユニバーサル・コミュニケーション・デザイン)で科学的に改善するサービスソリューションを提供しています。
こちらのUCDについて、気になる方はぜひ関連資料もご覧ください。
・関連資料のダウンロード
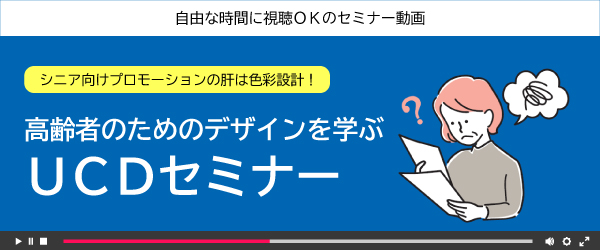 | 【ストリーミング動画】 ユニバーサルコミュニケーションデザインと高齢者のための情報デザイン 高齢者や多様な色覚者にも伝わりやすい情報デザインのための手法、 ユニバーサルコミュニケーションデザインについて解説します。 |