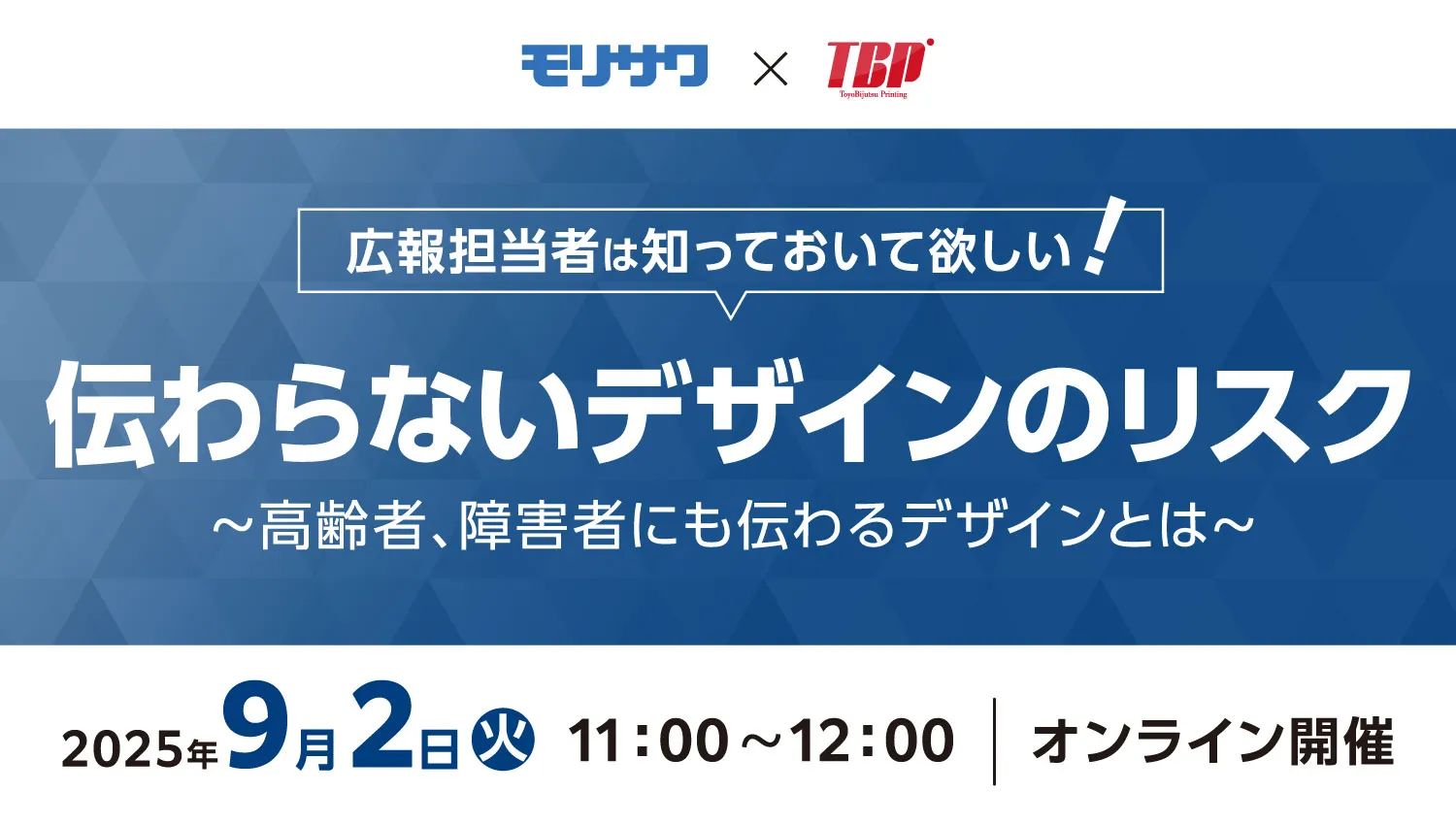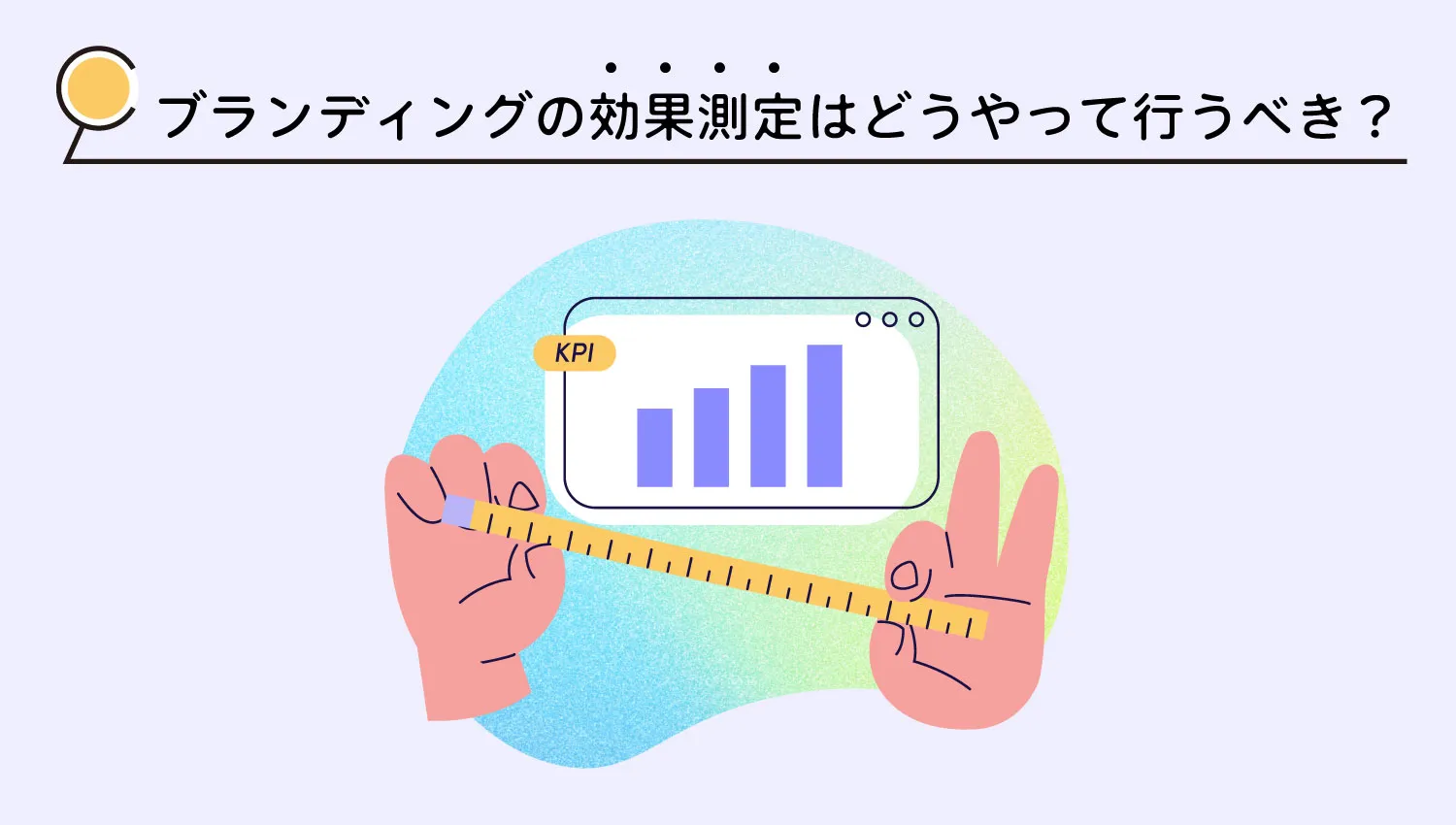製造業において、製品カタログは営業、マーケティング、そして顧客とのコミュニケーションを多角的に支える極めて重要なツールです。
以前は紙媒体が普通でしたが、Webサイト、デジタルカタログなど、その形態も多岐にわたり、メディア毎に様々な目的と役割を担っています。
本記事では、製造業の製品カタログ担当者が企画制作を進めるプロセスとして、重視すべき5つのステップを紹介します。
1 目的とターゲットの明確化:誰に何を伝えたいのか?
製品カタログの企画制作を始めるにあたり、まず最初にまとめておかなければいけないことが目的とターゲットの明確化です。
企画制作の根幹をなすものなので、この工程をおろそかにすると方向性を間違えて企画制作することとなり、どんなに優れたデザインや詳細な情報を盛り込んでもその効果は最大限発揮することはできなくなります。
1-1 カタログの目的を具体的に定義する
製品カタログは、その用途によって求められる情報や表現が大きく異なります。
- 営業用ツールとしてのカタログ:顧客への商談時に使用されることを想定し、製品の魅力や導入メリットを分かりやすく伝えることが重要です。
営業担当者が製品説明の補足資料として活用できるよう、視覚的な要素や、顧客が抱える課題に対するソリューション提示に重点を置きます。具体的な導入事例や、他社製品との比較優位性を示す情報も有効です。 - Web閲覧ツールとしてのカタログ(デジタルカタログを含む):潜在顧客が情報収集のためにオンラインでアクセスすることを想定します。SEOを意識したキーワード選定や、ユーザーが知りたい情報にすぐにたどり着けるような導線設計が不可欠です。
動画やアニメーション、3Dモデルなどのリッチコンテンツを積極的に導入することで、製品の機能や動作をより直感的に理解してもらうことができます。
ダウンロード可能なPDF版の提供も、利便性を高めます。 - 発注時の商品指定のためのツール:既に製品導入を検討している顧客や、リピート購入者が利用することを想定します。
製品の仕様、品番、価格、納期、注意事項など、正確かつ網羅的な情報が求められます。
誤発注を防ぐため、写真や図面を多用し、直感的に製品を特定できるような工夫が必要です。
オプション品や関連製品の情報も整理して提示することで、顧客の購買プロセスをスムーズにします。 - ブランディングツールとしてのカタログ:企業の技術力、信頼性、先進性をアピールし、企業イメージを向上させることを目的とします。
製品そのものの情報だけでなく、企業の理念、研究開発体制、品質管理体制などを盛り込むことで、顧客からの信頼を獲得します。
デザインや紙質にもこだわり、高級感や専門性を演出することも重要です。
これらの目的は単独で存在するわけではなく、複数の目的を兼ねることも多くあります。
例えば、営業用カタログがWebでも閲覧可能であり、かつ発注時の参考情報としても利用される、といったケースです。
どの目的に重きを置くのかを明確にすることで、コンテンツの優先順位付けや表現方法を最適化できます。
1-2 ターゲットユーザーの解像度を高める
製品カタログは、誰に向けて作られるのかによって、盛り込むべき内容や表現方法が大きく変わります。
ターゲットユーザーの解像度を高めるためには、以下の点を深く掘り下げて検討します。
- 業種・業界:顧客が属する業界特有の専門用語や課題を理解し、それに合わせた表現を用いることで、共感を得やすくなります。
例えば、医療機器メーカー向けであれば安全性や規制遵守、自動車部品メーカー向けであれば耐久性やコストパフォーマンスに重点を置くなどです。 - 役職・立場:購買担当者、技術者、経営者など、閲覧する人の立場によって求める情報が異なります。
技術者は詳細なスペックや技術資料を求める一方で、経営者は投資対効果や導入メリットに関心が高いでしょう。それぞれのニーズに合わせた情報を提供できるよう、情報の階層化や提示方法を工夫する必要があります。 - 知識レベル:製品や業界に関する知識レベルは様々です。専門用語を多用しすぎると、初心者には理解しづらくなります。
逆に、基本的な説明ばかりでは、熟練者にとっては冗長に感じられるかもしれません。
ターゲットの知識レベルに合わせた言葉遣いや説明の詳しさを調整することが重要です。専門用語には適宜解説を加えたり、専門家向けと初心者向けで情報を区分けするなどの配慮も有効です。 - 購買フェーズ: 製品カタログを閲覧する顧客が、どの購買フェーズにいるのかも重要です。
情報収集段階の顧客には、製品の概要やメリットを広く浅く伝える一方、比較検討段階の顧客には、競合製品との差別化ポイントや具体的な導入事例を示すことで、購買意欲を高めることができます。
これらの情報を明確にすることで、カタログ全体のトーン&マナー、デザイン、そして盛り込むべきコンテンツの方向性が定まり、ターゲットに響くカタログを制作するための基盤が築かれます。
2 コンテンツの企画と構成:何をどのように見せるか?
目的とターゲットが明確になったら、次に具体的なコンテンツの企画と構成に進みます。
製品カタログの価値は、単に製品情報を羅列するのではなく、いかに顧客の課題を解決し、製品の魅力を効果的に伝えられるかにかかっています。
2-1 顧客視点での情報設計
製品カタログは、メーカーの「伝えたいこと」だけでなく、顧客の「知りたいこと」を優先して情報設計することが重要です。
- 課題解決型のコンテンツ:顧客が抱える具体的な課題を提示し、それに対して自社製品がどのように貢献できるのかを明確に示します。
例えば、「生産効率が上がらない」「品質が安定しない」といった課題に対し、製品導入によって得られる具体的な改善効果を提示します。 - 導入メリットの具体化:単なる機能説明に終始せず、「導入によってコストを〇〇%削減できる」「〇〇時間の作業時間を短縮できる」「品質不良を〇〇%低減できる」など、数値や事例を用いて具体的なメリットを提示します。
顧客は製品そのものよりも、それがもたらす成果に関心があります。 - 使用シーンの提示:製品がどのような環境で、どのように使用されるのかをイメージしやすいように、写真やイラスト、動画などで具体的な使用シーンを提示します。
特に、BtoB製品では実際の稼働状況を見せることで、顧客は導入後のイメージを具体的に掴みやすくなります。 - Q&A形式の導入:顧客が抱きやすい疑問を想定し、Q&A形式で回答を掲載することで、顧客の疑問をその場で解消し、次のアクションへと促します。
技術的な質問や導入後のサポートに関する質問などが考えられます。
このように、製品による課題解決のシーンを想起させることが望ましいですが、受発注にあたって特定の商品を指定することを目的としたカタログの場合には違った観点を持つ必要があります。
優先されるのは検索性と見やすさ、わかりやすさとなり、シンプルでメリハリの利いた情報設計が求められます。
2-2 製品情報の効果的な表現
製品情報の羅列では、顧客はカタログを見るのに飽きてしまい、必要な情報に目を通すことをやめてしまうかもしれません。
情報を分かりやすく、魅力的に伝えるための工夫が必要となります。
- 高品質な写真・イラスト:製品の細部までわかる高解像度の写真や、機能や構造を視覚的に理解できるイラストは不可欠です。
製品の魅力を最大限に引き出すために、プロのカメラマンによる撮影や専門のイラストレーターへの依頼を検討しましょう。
特に、製品の独自性や差別化ポイントを強調するカットは重要です。 - 図解やグラフの活用:複雑な技術的な内容や、数値データは、文字ばかりでは理解しにくいものです。
図解やグラフを積極的に活用することで、視覚的に分かりやすく情報を伝えることができます。
例えば、製品の内部構造、性能比較データ、導入効果などを図解やグラフ、もしくは3DCGなどで示すと効果的です。 - 比較表の作成:複数の製品ラインナップがある場合や、オプション品が多い場合は、比較表を作成することで、顧客は自身のニーズに合った製品を効率的に見つけることができます。
性能、機能、価格などの主要な比較項目を分かりやすく整理しましょう。 - ストーリーテリング:製品開発の背景や、製品に込められた想いをストーリーとして語ることで、顧客の感情に訴えかけ、製品への愛着や信頼感を醸成することができます。
例えば、開発者のインタビューや、製品が社会に貢献する様子を描くなどが考えられます。
2-3 情報の階層化とナビゲーション
カタログの情報量が多くなるほど、顧客が目的の情報にたどり着きにくくなります。
情報の階層化と分かりやすいナビゲーションが重要です。
- 目次と索引:特に情報量の多いカタログでは、目次と索引は必須です。
目的の情報に迅速にアクセスできるよう、分かりやすいキーワード設定とページ表記を心がけましょう。 - セクション分けと見出し:製品カテゴリー、用途別、技術別など、明確なセクション分けを行い、各セクションに分かりやすい見出しをつけます。
これにより、顧客は自分が興味のある部分を効率的に閲覧できます。 - 関連情報への誘導:製品情報だけでなく、導入事例、FAQ、お問い合わせ先、関連製品など、顧客が必要とする情報への導線を明確にします。
Webカタログであれば、内部リンクやCTA(Call To Action)ボタンを効果的に配置します。
紙媒体であれば、QRコードを活用してWebサイトへ誘導することも有効です。
3 デザインとレイアウト:視覚的に魅力を伝える
デザインとレイアウトは、製品カタログの第一印象を決定づけ、読み手の興味を引きつける上で極めて重要な要素です。
どんなに素晴らしい情報が盛り込まれていても、デザインが魅力的でなければ、手に取ってもらえません。
3-1 ブランドイメージの統一
製品カタログは、企業の顔となるツールの一つです。企業のブランドイメージを統一し、一貫性を持たせることが重要です。
- コーポレートカラー、ロゴの活用:企業のコーポレートカラーやロゴを効果的に配置し、一目で自社製品と認識できるようにします。
ブランドガイドラインに沿った色使いやフォント選定を徹底します。 - トーン&マナーの統一:専門的で信頼性の高いイメージ、革新的で先進的なイメージなど、カタログ全体のトーン&マナーを統一します。
これにより、企業が伝えたいメッセージがより明確に伝わります。
例えば、精密機器であれば洗練されたクリーンなデザイン、重機であれば力強く堅牢なデザインなど、製品や企業特性に合わせた表現が求められます。 - 写真やイラストのスタイル統一: 使用する写真やイラストも、カタログ全体の雰囲気に合わせて統一感を持たせます。
統一感のない画像は、プロフェッショナルさに欠ける印象を与えかねません。企業としてのブランドガイドが整備されていることが重要です。
整備されていない場合は制作会社に相談し、製品カタログ用のデザインルールをあらかじめ決めておくのが良いでしょう。
3-2 読みやすさと視認性の確保
デザインは見た目の美しさだけでなく、情報の伝達効率を高める役割も果たします。
ターゲットユーザーには様々な年代が含まれることもあり、色弱者も含まれることにもなります。ユニバーサルな視点で伝わるデザイン配慮がされていることが望ましいです。
- 適切なフォントの選択とサイズ:読みやすいフォントを選び、適切な文字サイズで配置します。
特に、技術情報やスペック表など、情報量の多い箇所では、小さすぎない文字サイズと行間を確保することが重要です。
欧文フォントと和文フォントの組み合わせも考慮します。 - 余白の活用:情報で埋め尽くされたカタログは、窮屈で読みにくい印象を与えます。
適度な余白を設けることで、情報を際立たせ、視覚的な快適さを提供します。
これにより、読者の視線誘導もスムーズになります。 - 情報のグルーピングと視覚的強調:関連性の高い情報はグループ化し、見出しや罫線、背景色などで視覚的に区別します。
重要なポイントは太字にしたり、色を変えたりすることで、読者の注意を引きつけ、メッセージを効果的に伝えます。 - グリッドシステムの活用:レイアウトの統一性を保ち、情報を整理するためにグリッドシステムを導入します。これにより、規則正しく配置された情報は、視覚的に安定感を与え、読みやすさを向上させます。
3-3 クロスメディア展開を意識したデザイン
今日では製品カタログは、紙媒体だけでなく、Webやタブレットなど様々なデバイスで閲覧されることを前提に設計する必要があります。
レスポンシブデザイン(Webカタログ): Webカタログの場合、PC、タブレット、スマートフォンなど、様々な画面サイズに対応できるレスポンシブデザインを採用します。
これにより、どのデバイスからアクセスしても快適に閲覧できます。
- インタラクティブ要素の配置(デジタルカタログ):デジタルカタログでは、動画の埋め込み、3Dモデルの表示、製品の回転ビュー、関連ページへのリンクなど、インタラクティブな要素を積極的に導入することで、紙媒体では得られない体験を提供し、顧客の理解を深めます。
- 印刷とWebでの見え方の調整:紙媒体とWebで同じデザインを用いる場合でも、色味や解像度など、それぞれの媒体特性を考慮した調整が必要です。
印刷では鮮やかに見える色が、Webではくすんで見えることもあるため、両方の見え方を意識したデザインが必要です。
ただし、相互に依存し過ぎたクロスメディア設計をしてしまうと、デジタルメディアが苦手な年齢層は必要な情報にたどり着けなくなる可能性が高くなります。
クロスメディアは目的ではなく、情報を補ったり利便性を高めるための手段として活用するようにしましょう。
4 制作プロセスと効果測定:PDCAサイクルの確立
製品カタログの企画制作は、一度作って終わりではありません。
継続的な改善を行うことで、その効果を最大化できます。
4-1 専門家との連携と役割分担
製品カタログ制作には、様々な専門知識が必要です。
社内リソースだけで全てを賄うのが難しい場合は、外部の専門家との連携を検討しましょう。
- 企画・編集:自社製品を最も深く理解している製品担当者やマーケティング担当者が中心となり、カタログの目的、ターゲット、コンテンツの方向性を策定します。
- ライティング:製品の技術的な専門知識を持ち、かつ顧客に響く言葉で表現できるライターを選定します。
専門用語の羅列ではなく、メリットや価値が伝わる文章を作成することが重要です。 - デザイン・DTP:視覚的に魅力的で、かつ読みやすいデザインを作成できるデザイナーやDTPオペレーターが必要です。
特に、製造業の製品は複雑な構造を持つことが多いため、図解やイラストの表現力が問われます。 - 写真撮影:製品の魅力を最大限に引き出すためには、プロのカメラマンによる高品質な写真が不可欠です。
製品の特長を理解し、適切な構図や照明で撮影できるプロフェッショナルを選びましょう。 - 印刷・製本(紙媒体の場合):適切な紙質、印刷方法、製本方法を選定し、最終的な品質を確保します。
耐久性や高級感など、カタログの用途に応じた仕様を検討します。 - Webシステム構築(Webカタログの場合):Webサイト制作会社やCMSベンダーと連携し、ユーザビリティが高く、SEOにも配慮したWebカタログを構築します。
各役割を明確にし、専門家と密に連携することで、質の高い製品カタログを効率的に制作できます。
4-2 制作スケジュールと予算管理
製品カタログ制作は、多くの工程と関係者が関わるプロジェクトです。
- 詳細なスケジュール策定:企画、情報収集、ライティング、写真撮影、デザイン、校正、印刷(Web公開)など、各工程の期間と担当者を明確にした詳細なスケジュールを策定します。
- 進捗管理: 定期的なミーティングや進捗報告を通じて、スケジュール通りに進行しているかを確認し、遅延が生じた場合は速やかに対応します。
- 予算の見積もりと管理:企画、ライティング、デザイン、写真撮影、印刷費(Webシステム構築費)など、すべての費用を正確に見積もり、予算内で収まるように管理します。
追加費用など予期できなかった費用に備えて、予備費を設けることも重要です。
4-3 効果測定と改善(PDCAサイクル)
製品カタログは、制作して終わりではありません。その効果を測定し、継続的に改善していくことが重要です。
測定指標の設定
- 営業用カタログ:商談時の顧客反応(興味度、質問内容)、成約率の変化、営業担当者からのフィードバックなど。
- Web閲覧ツール:アクセス数、滞在時間、PV数、ダウンロード数、お問い合わせ数、CVR(コンバージョン率)、キーワード検索からの流入数など。Google Analyticsなどのツールを活用して詳細なデータを収集します。
- 発注ツール:発注時のエラー率、発注にかかる時間、顧客からの問い合わせ内容など。
- 効果測定と分析:設定した指標に基づき、定期的に効果を測定し、分析します。期待通りの効果が得られているか、課題はないかを検証します。
- 改善点の特定と実行:分析結果に基づき、改善点を特定します。例えば、特定のページの離脱率が高い場合は、コンテンツの内容やデザインを見直す。問い合わせが少ない場合は、CTAの配置やメッセージを改善するなど、具体的な施策を実行します。
- PDCAサイクルの確立:企画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)のPDCAサイクルを回し、製品カタログを常に最適化していくことで、その効果を最大化し、企業のビジネス成長に貢献します。
顧客からのフィードバックを積極的に取り入れることも、改善の重要なヒントとなります。PDCAはWeb改善には反映しやすく効果が出やすいです。しかし紙媒体は在庫している数がなくならない限りPDCAを回すことが困難です。
紙媒体においてもPDCAを重視する場合には、従来の大量発行型のオフセット印刷方式から、少数発行型のオンデマンド印刷(デジタル印刷)に切り替えても良いでしょう。
5 デジタル化への対応
スマホの普及もありデジタル化が進んだ現代において、製品カタログのデジタル化は避けて通れないテーマです。
紙媒体の良さを活かしつつ、デジタル化のメリットを最大限に引き出す視点も重要です。
5-1 デジタルカタログの活用
デジタルカタログは、紙媒体にはない多くのメリットを提供します。
- アクセシビリティと拡散性:いつでもどこでも閲覧可能であり、容易に共有・拡散できます。
- コスト削減:印刷費や郵送費を削減できます。
- 情報更新の容易さ:製品の仕様変更や新製品の追加があった場合でも、迅速かつ容易に情報を更新できます。
- 多様なコンテンツ:動画、アニメーション、3Dモデルなど、リッチコンテンツを埋め込むことで、製品の理解度を高めます。
- データ分析:閲覧数、滞在時間、クリックされた箇所など、詳細なデータを取得・分析することで、コンテンツの改善に繋げられます。
- 環境への配慮:ペーパーレス化により、環境負荷の低減にも貢献できます。
ただし、デジタルカタログは紙媒体の代替品ではなく、それぞれの特性を理解し、適切な使い分けや連携が重要です。
例えば、営業商談の冒頭は紙媒体で印象を与え、詳細な情報はデジタルカタログで補完するといった活用方法も考えられます。
5-2 オムニチャネル戦略の中核として
製品カタログは、企業のマーケティング活動全体の中で、オムニチャネル戦略の中核を担うツールとなりえます。
- Webサイトとの連携:カタログからWebサイトへの誘導、Webサイトからカタログへの誘導をスムーズにし、顧客が求める情報に効率的にアクセスできるようにします。
- CRMとの連携:カタログの閲覧履歴やダウンロード履歴を顧客情報と紐付けることで、顧客の興味関心を把握し、パーソナライズされた営業・マーケティング活動に繋げます。
- SNSとの連携:製品カタログの一部をSNSでシェアしたり、SNS広告からカタログへ誘導したりすることで、新たな顧客層へのリーチを拡大します。
- 展示会・イベントでの活用:展示会では、紙媒体のカタログを配布しつつ、会場限定のQRコードからデジタルカタログへ誘導し、アンケート回答や資料ダウンロードを促すなど、オンラインとオフラインを融合した戦略が有効です。
まとめ
製造業における製品カタログは、単なる製品情報の集約ではなく、企業のブランドイメージを形成し、顧客との関係を構築し、最終的な購買行動へと導くための戦略的なツールです。
目的とターゲットの明確化を起点に、顧客視点でのコンテンツ企画と魅力的で読みやすいデザインを追求し、PDCAサイクルによる継続的な改善を行うこと。そして、デジタル化への対応とオムニチャネル戦略の一環として位置づけること。
これらのポイントを深く掘り下げ、実践することで、製品カタログは単なる営業資料の枠を超え、企業の成長を力強く後押しする、示唆に富んだ強力なマーケティングツールとなるでしょう。
製品カタログ担当者の皆様には、本記事がその企画制作の一助となれば幸いです。
・関連資料のダウンロード
 | ヨミヤスUCD診断 診断レポートサンプル 文書の見やすさを自動判定するツール「ヨミヤスUCD診断」。 診断レポートと、必要な費用についてご紹介した資料をご用意しました。 |