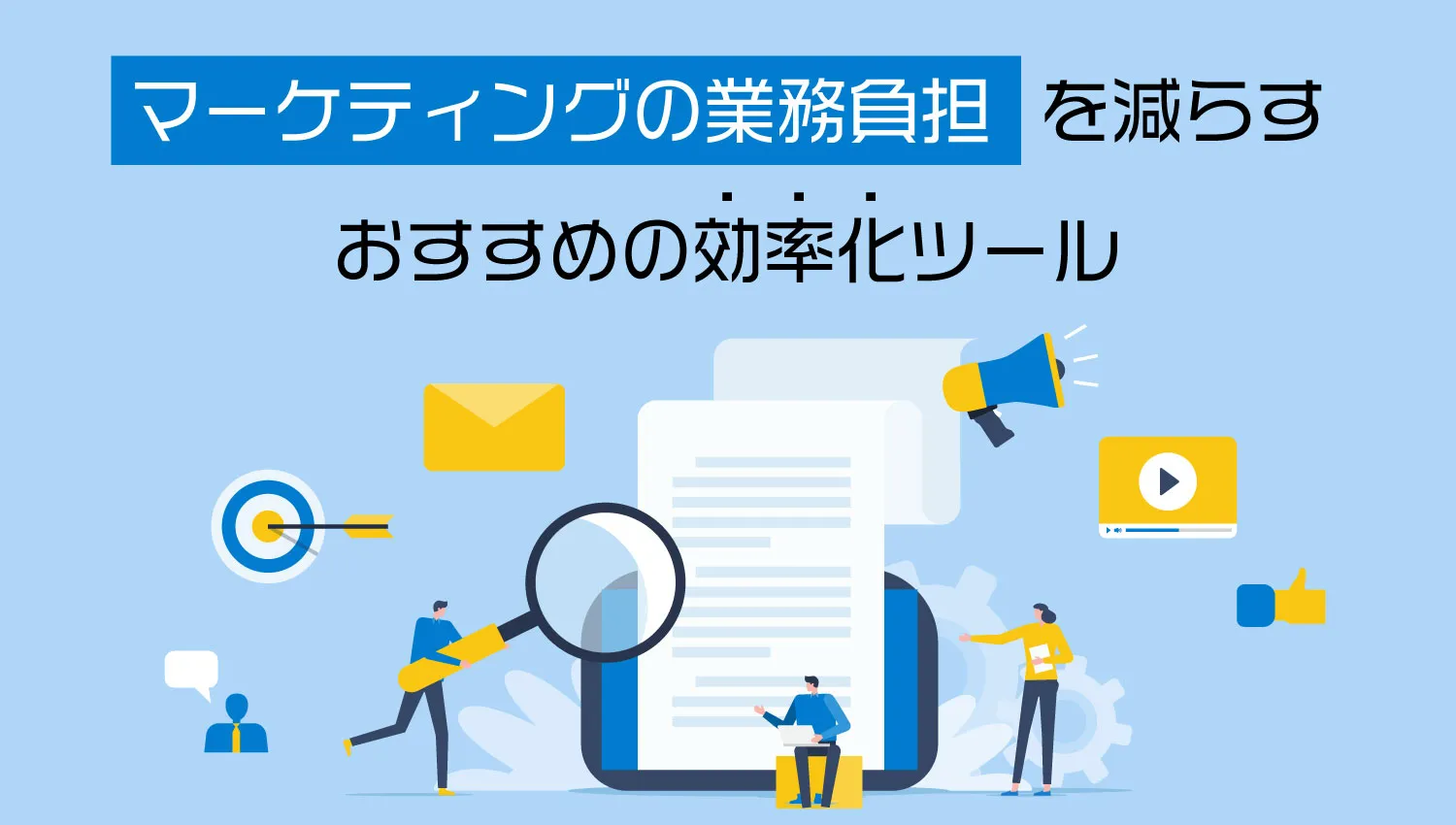「工場見学」と聞くと、多くの人が知っているような大手企業が郊外の大規模な施設で実施している様子を想像する方も多いかと思われます。
しかし工場見学はブランディングやCRMなど様々な効果を企業にもたらしてくれるため、どんな企業であっても実施することで様々なメリットが見込めるんです。
そこで今回は工場見学を行うことで企業にもたらすおもなメリットや、実施の流れやポイントについてまとめました。
工場見学がどのようなものか、まずは簡単におさらい
工場見学はユーザーや取引先企業など社外の不特定多数の方に工場や製造拠点を見てもらい、生産過程や運営状況などを具体的に知ってもらうための取り組みです。
食料品や自動車などのメーカーが家族連れや学校などに向けて行う見学ツアーのイメージが強いかもしれませんが、工場見学はステークホルダーなど特定のターゲットにのみ向けて行うものなど様々な性質のものがあります。
ただ実際の様子を見てもらうことで、社外の方にメーカーとしての技術の高さや生産のこだわり、企業としてのあゆみなどを知ってもらうという根本的な狙いは共通しています。
工場見学はおもに以下のパートで構成されていることが多いです。
- 受付(あいさつや安全上の注意などの説明)
- 映像・パネルによる展示(工場・企業の概要や歴史の説明)
- 場内見学(製造ライン・実験設備などの見学)
- 体験企画(試食やシミュレータなどによる簡易的な体験)
- 講演・Q&A(工場関係者による説明や質疑応答)
- 特典配布(サンプル品やグッズといった謝礼品の提供)
工場見学を実施することによる5つのおもなメリット
工場見学のメリット① 企業知名度やブランドイメージを上げられる
工場見学に来てもらうことは多くの方に自社の活動を知ってもらう機会になるだけでなく、より良いブランドイメージを持ってもらうきっかけにもなります。
特に材料の選定や仕上げ加工などでのメーカーとしてのこだわりを積極的に伝えることで、「高級感」や「信頼感」といったブランドイメージを抱きやすくなります。
ブランドイメージが向上すれば、こちらから働きかけなくても口コミやネットでの投稿などによりひとりでに会社の認知が広がってくれる可能性も期待できます。
工場見学のメリット② 社会貢献活動としてのアピール材料になる
周辺地域への環境的な影響の抑制や労働者の作業環境の改善などに取り組む姿勢を、ステークホルダーなどに見てもらうことで自社のCSV経営をアピールすることができます。
CSV経営の取り組みをWEBサイトなどで紹介している企業も多いと思いますが、工場見学もCSV経営を紹介して自社のイメージを向上させるチャネルとして活用できます。
特に工場誘致のお礼などとして地元住民に向けた工場見学を開催することで、地域社会と共存して共に発展を目指す会社のすがたを社外の方々に見せることができます。
工場見学のメリット③ 既存顧客のエンゲージメントを高められる
すでに製品を愛用している顧客や取引をしている企業の方に工場見学を通じて自社の最新事情を紹介することで、自社へのエンゲージメントをより強めることができます。
自社の製品を継続的に利用してもらうためには競合他社の製品との差別化が重要ですが、工場見学は社内の方しか知らない強みを改めて顧客に伝えるいい機会といえます。
また個別で商談をとれる時間を設けることで、現在使っている製品への意見を聞きだしたり要望をもとに新たな製品を提案したりすることも可能です。
工場見学のメリット④ 人材募集のためのPRツールとして使える
就職活動中・転職中の方に工場に来てもらい実際に作業している様子を見せることで、どういう企業か知ってもらうツールとして人材募集に活用できます。
食堂など従業員向けの施設が充実している点や工場の内部の清潔さが保たれている点など労働環境の面もアピールできれば、さらにPR効果が高まります。
また就活生にとっても実際に自社の様子を見ることで、入社前後のイメージのミスマッチが発生しにくくなり、採用後すぐ離職してしまうリスクが減らせます。
工場見学のメリット⑤ 会社や製品に対するリアルな意見が聞ける
工場見学に来てくれた方にアンケートやインタビューなどを行うことで、自社や製品に対するリアルな声を集めて課題やニーズの発見につなげることができます。
また工場見学の来客の動線や視線の動きなどから、ユーザーは製品のどういう部分を気にしやすいか分析できるかもしれません。
手間や時間をかけずに効率よくいろいろな意見を聞けることから、工場見学はマーケティング的な意味でも大きなメリットがあるのです。
このように工場見学にはメーカー側にとっても様々なメリットがあります。
そんな工場見学を実際に開催する際の流れや注意点をまとめてみました。
工場見学の企画段階から開催後までの7つの大まかなフロー
開催の目的やターゲットの明確化
工場見学を開催するにあたり、まずはどんな方に来てもらって何をしてもらいたいか目的やメインターゲットをしっかり決めておきましょう。
目的がはっきりすれば誰に向けて工場見学を開催したいのか、ターゲットのペルソナ像もおのずと見えてきやすくなります。
基本計画の策定と部門間の連携
工場見学の日程やスタッフ編成、そして一番重要な見せたい内容といった基礎的な事柄をしっかりと決めていきます。
特に工場従業員との間では、工場見学の内容が当日の作業の妨げにならないためにはどうすればいいか連携することが重要です。
見学ルートや当日のスケジュールの選定
工場見学当日はどういう順路でめぐるのか、何時にどこで何のプログラムを行うか具体的に設定していきます。
パネルやスクリーンなどを展示するスペースが十分にあるか、工場内をスムーズに見学できるのは一度に何名までかといったことも忘れずに確認しましょう。
展示物や配布資料などの準備
写真パネルや映像用のスクリーンといった当日の展示で使うものや、パンフレットや会社案内など当日配布する冊子を漏れのないよう準備していきます。
海外企業の日本法人の方や就活中の大学生など特定のメインターゲットによりささりやすいよう、冊子の内容や表現を適宜工夫してみるのもおすすめです。
予約管理・リハーサル・事前準備
予約参加制の工場見学を開催する場合は、WEBや電話から来た申し込みをしっかり共有して事前の準備に支障がでないようにしておきます。
貴重品や手荷物はどこに預けるか、見学ルート上にお手洗いがあるかなど開催当日に向けて細かな部分まで考えながら準備を進めましょう。
工場見学当日の対応・案内
工場見学当日では展示に用いた機器の不具合や病欠などによる担当スタッフの欠員など、様々なトラブルが起こり得るため、臨機応変に対応する姿勢が何よりも重要になります。
また最寄り駅から工場まで距離がある場合や当日の天候が悪くなった場合、駅やバスターミナルなどから社用車による送迎をおこなうのもおすすめです。
開催後のアフターフォロー
当日開催したアンケートの集計や来てくれた方へのお礼メールの配信など開催後の対応を行い、来てくれたリード顧客との関係性を維持できるようにしましょう。
また今後も工場見学を開催するのであれば、当日気づいた課題点をまとめて次の実施までにどう改善したらいいか忘れずに考えてみてください。
工場見学を開催する上で絶対に注意が必要なポイント
① 来客がケガなどを負わないよう安全性は必ず確保しておく
工場には数多くの機械や薬品などがあるため、何らかの要因によって来客がケガや所持品の破損を負うリスクも十分考えられます。
立入禁止の区域を設定する、ヘルメットや安全靴を着用してもらうといった対策をとって来てくれた方の安全は必ず保たれるようにしておきましょう。
② 社外秘の情報は来客の目につかないよう離して収納しておく
顧客の機密情報や開発中の新製品のデータなど社外の人間に漏らしてはいけない情報は、見学ルートからなるべく遠ざけて来客の目につかない場所に保管しましょう。
階段ではなくエレベータで移動してもらう、特定の階のお手洗いのみを利用してもらうなど来客が行ける範囲を最小限にとどめる工夫がおすすめです。
③ 従業員の作業を妨げる行為や迷惑となる行為を禁止しておく
工場見学を実施している間も、製造ラインでは通常通りの生産作業が行われています。
工場内での私語・飲食・写真撮影など、従業員の作業を妨げたり彼らが不快に感じたりするような行動を取る人の出ないよう、はっきりと禁止事項を明記しておきましょう。
工場見学にはメーカーにとってもメリットがたくさんある
工場見学には製品のことを知ってもらうだけでなく、人材募集や既存顧客の関係維持など様々な用途のツールとして活用できます。
開催する際は工場従業員など外部との連携を密に取りながら、より製品の魅力が伝わるように見てもらうには何をどういう経路で見せるべきかしっかり考えることが大切です。
また来客の安全性を確保できる見学ルートにしたり会社の取引顧客の個人データなどが漏洩しないよう社外秘の情報は離して保管したりといったことも必ず対策をとりましょう。
こうしてリアルに作業の様子を見てもらうことで、エンゲージメントや顧客価値の向上につながる体験を社外の方に提供できるのが工場見学の特徴といえるでしょう。
・関連資料のダウンロード
 | 工場見学やオンライン展示会で活躍する VR活用方法 本資料では3Dカメラで撮影した空間をWEBコンテンツ化するサービス「VR360」の説明と、工場見学やオンライン展示会でどのように活用できるかのアイディアを掲載しています。 |