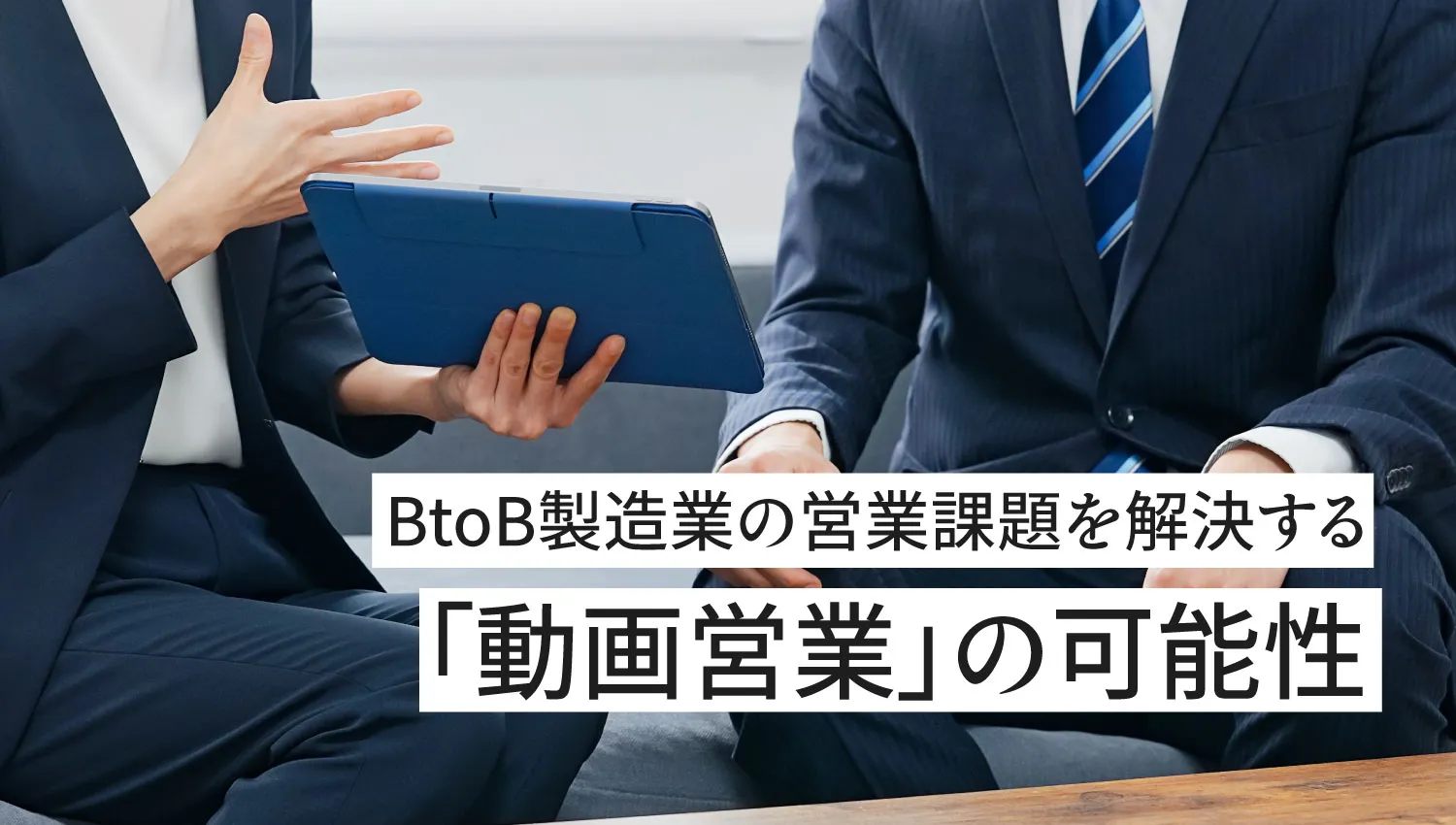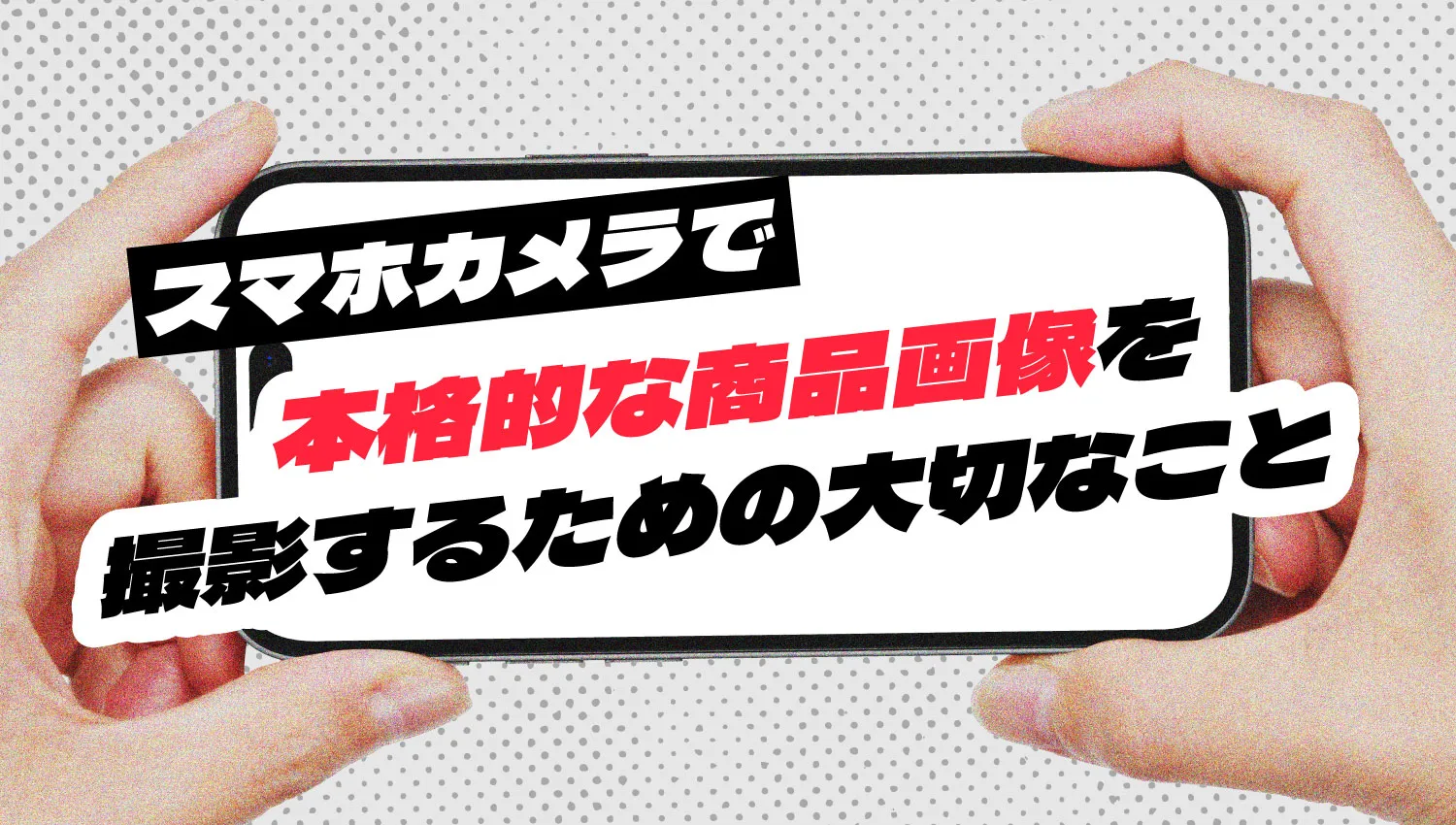大阪万博にて経済産業省が体験型のパビリオンを出展するなど、「サーキュラーエコノミー」という新しいかたちの経済システムが近年注目を集めています。
「サーキュラーエコノミー」とは循環経済という意味なのですが、サステナブルな社会を実現させるためには避けて通れない考え方といえます。
実際に日本をはじめ世界のあらゆる国では、政府や大企業が連携しながらサーキュラーエコノミーの実現に向けて動き出しています。
そこで今回はサーキュラーエコノミーについて事例もあわせて見ていきたいと思います。
サーキュラーエコノミーとは「サステナブルな社会経済のあり方」
サーキュラーエコノミーは工業製品のライフサイクルを見直して取り組むことで、限りある資源をより循環することを目指す経済システムです。
そのためには製造加工の段階で出る産業廃棄物や、製品の持続性や再利用性を高めてゴミとして廃棄される分を減らすための取り組みが不可欠となります。
このサーキュラーエコノミーに対して、従来の大量消費・大量廃棄の経済システムは「リニアエコノミー(線形経済)」と呼ばれていて、これは製品の素材採取から製造、消費者が利用して廃棄するまで不可逆的な一本の線で表せることから来ています。
リニアエコノミーは製品を廃棄する責任が消費者に移行されるため、環境に配慮されてつくられたものでも再資源化せず廃棄されて自然環境に悪影響を及ぼすリスクもあります。
そのためサーキュラーエコノミー実現のためには製造業者だけでなく、製品に携わるすべての人が再資源化を意識することが求められます。
サーキュラーエコノミー実現のためのアクションの例
サーキュラーエコノミーの概念を説明する際、よく使われるのが「バタフライダイアグラム」です。
これは資源のサイクルを可視化した図で、左側に木材や水など再生可能な資源の循環を表すサイクル、右側に石油や鉱物など有限な資源の循環を表すサイクルが蝶の羽のような形で描かれています。
例えば右側のサイクルでは、大量廃棄による環境汚染や資源の浪費を抑えるために以下のアクションが例示されています。
- 製品を適切に管理したり修理したりしながら使い続けることで利用寿命を伸ばす
- 製品を共有することで原材料としての希少資源の使用量を減らす
- 製品をリサイクルすることで資源として再生利用できるようにする
「サーキュラーエコノミー」のもととなった「3R」
サーキュラーエコノミーが誕生したきっかけとなった概念に、「3R」があります。
3Rは「Reuse(繰り返し使う)」「Reduce(ごみを減らす)」「Recycle(ごみを再利用する)」の頭文字の総称で、日本では2000年の循環型社会形成推進基本法をきっかけに広まった言葉です。
サーキュラーエコノミーはこの3Rの実現により、天然資源の不可逆的な消費のしくみをあらためて、持続可能な社会システムを実現することを目指しています。
大量生産、大量消費が当たり前だった社会のかたちが変わることで、将来的に今では当たり前の私たちの生活スタイルも大きく変容していくかもしれません。
そのため企業や行政の取り組みだけでなく、社会全体で価値観や考え方を刷新していくことがサーキュラーエコノミーの実現でとても重要だといえるでしょう。
「サーキュラーエコノミー」は日本に古くから根付く考え方
サーキュラーエコノミーという言葉は欧米で誕生したものですが、すでにそれに近い考え方は江戸時代の日本にすでにありました。
当時の日本は鎖国下にあり外国から資源を調達できないにも関わらず、世界有数の人口過密地帯であったため、現在ほど資源や物資が自由に活用できるわけではありませんでした。
そのため人々は限られた資源を有効活用する技術を考案するようになり、例えばボロボロになった着物は捨てずにおむつや雑巾などに再利用され、最終的には燃やして灰となって肥料や染料など様々な用途に活用されました。
一度利用し終えたものも修理して再利用したり別の用途に転用したりして、最後も資源としてなるべく活用するといった考え方は、まさしく現代のサーキュラーエコノミーに通じるといえますね。
製造業におけるサーキュラーエコノミーの取り組み
近年、大企業や自治体が連携してサーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組みを行う事例が国内でも数多くみられています。
サーキュラーエコノミーのための取り組み①:富士フイルムグループ
富士フイルムグループでは使用済みの複合コピー機を修復しながら、再生機として再生産するための新たな設備をフィリピンの製造拠点に建設しています。
同社では1995年に製品のライフサイクル全体にかかわる循環型生産システムを構築するなど、長年グループ全体でリサイクルに対する取り組みを続けてきました。
この製造拠点では複合機を部品単位で細かく分解して清掃・修理したのち、基準を満たす部品を再利用することで資源循環に寄与した生産システムを実現しています。
再生機の部品再利用率は最大で84%にものぼり、資源消費や廃棄処分で排出される二酸化炭素を抑えながらも、新たな生産システムによるグループ全体での生産体制の強化も目指しています。
サーキュラーエコノミーのための取り組み②:ブリヂストン
タイヤメーカーのブリヂストンでは、すり減って返却されたタイヤのトレッドと呼ばれる表面部分を張り替えてリトレッドタイヤとして再生産するソリューションを展開しています。
同社のタイヤを生産後にリトレッドタイヤとして2回作り直した場合と、新品のタイヤを3回生産する場合で、原材料の使用量や廃棄処分によるCO2の排出量も半分ほどにおさえることができます。
自動車や飛行機など人命を載せて運ぶ輸送機械に使われるため、リトレッドタイヤは環境面に優れただけでなく新品タイヤと同様の安全性や耐久性を満たす商品として提供されています。
また原材料の使用をおさえている分、リトレッドタイヤは新品タイヤよりも価格が低めなのも特徴で、新品タイヤの9割~5割ほどの値段で購入できるといわれています。
サーキュラーエコノミーのための取り組み③:タイガー魔法瓶社
ステンレス製品メーカーのタイガー魔法瓶社は2021年、使用済みのステンレスボトルを回収して資源として再利用する取り組みを京都府亀岡市と連携してはじめました。
家庭で不要になったステンレスボトルは、亀岡市内で集められたあとリサイクル業者により処理されて再生ステンレス材や再生樹脂へと生まれ変わり、同社の電気製品の素材として再活用されます。
同社では2020年より持続可能な社会の実現に向けて「NO・武装鉱物」「NO・フッ素コート」「NO・丸投げ生産」「NO・プラスチックごみ」の4つの約束を掲げています。
廃棄された製品を資源として再利用することで、ゴミの発生を抑えるだけでなく違法採掘や児童労働など反社会的なサプライチェーン由来の資源を使用しないことにもつながります。
サーキュラーエコノミーのための取り組み④:ミヤモリ
富山でアパレル用品を製造しているミヤモリでは、2023年に衣服を作る際に出てくる生地のあまりを有効活用した鉛筆を開発して日本文具大賞優秀賞を受賞しました。
洋服を作るときに処分されている裁縫くずを環境負荷の少ない蒸し焼きの技法で炭化させることで、鉛筆の芯として有効活用できるようにしています。
同社の工場では毎年20トンもの裁縫くずが廃棄されており、鉛筆として再利用することで焼却処分による二酸化炭素の排出を抑えることができます。
同社ではほかにも元々捨てられていたものであるハトムギのぬかからぬか油を取り出して原料に活用した、衣類や化粧品のブランド「ネルコッチャ」シリーズを立ち上げるなどアパレル企業ならではの方法で資源循環に貢献しています。
サーキュラーエコノミーのための取り組み⑤:日立建機
大手建設機械メーカーの日立建機は2021年、豪雨災害により水没してしまった油圧ショベルカーを修復して新車と変わらない機能性を持つ中古車両としてよみがえらせました。
同社では1970年代より資源循環のための使用済み純正部品のリサイクルに取り組んできましたが、車両1台まるごと再生させる取り組みは初めてとなります。
回収時にはエンジンが起動できない状態だったのが、すべての部品を取り外して汚れや傷を丁寧に除去したり独自技術を適用した再生部品を搭載したりすることで性能基準を満たす中古車両「PREMIUM USED」として生まれ変わっています。
PREMIUM USEDは国内だけでなく新興国にも流通しており、海外への販路拡大と現地での大型機械の廃棄による環境への悪影響の抑制につながっています。
持続可能性と経済の発展性を両立させる「サーキュラーエコノミー」
サーキュラーエコノミーは、限りある資源を再利用やリサイクルといったかたちで無駄なく有効的に使いながら経済発展を目指すシステムを指す言葉です。
3Rの考え方をベースに、企業や行政、消費者などが一体となって資源循環のサイクルを回していくことによってサーキュラーエコノミーの実現につなげられます。
すでに日本では江戸時代からサーキュラーエコノミーに近い考えが定着しており、現在でも様々な業種の企業や自治体が連携して実現に向けた取り組みを行っています。
他社や自治体などと連携することで中小企業でも取り組みやすいサーキュラーエコノミー、今後も様々な企業でユニークな事例がみられるかもしれないですね。
・関連資料のダウンロード
 | カーボンオフセット価格表 カーボンオフセットをおこなった印刷にはいくらかかるのか価格の目安をまとめました。 |