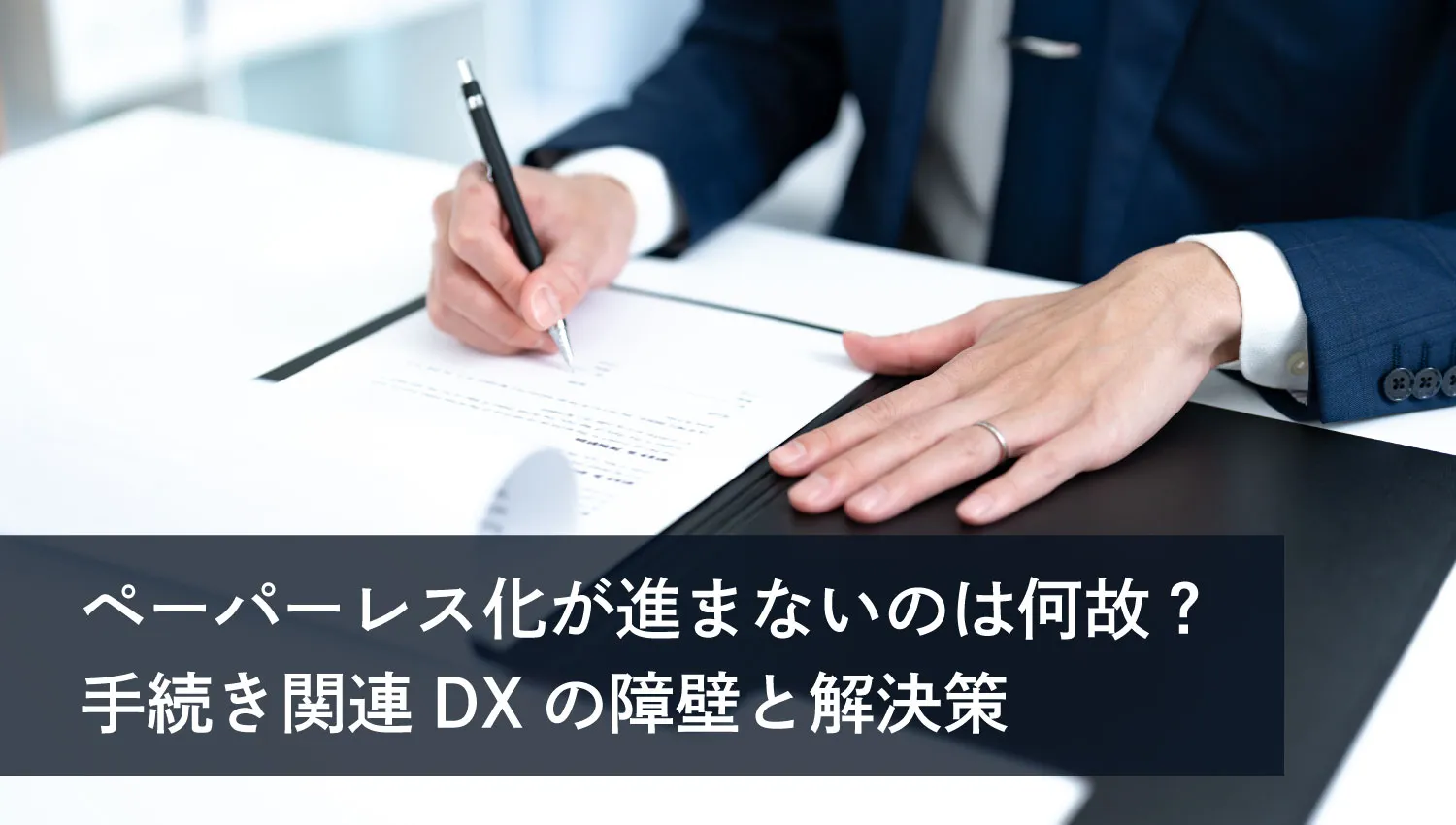会社のコンテンツとしてオウンドメディアを管理するのは、常に締め切りや期日との闘いといえます。
なるべく頻繁に記事を更新してリードの関心をつなぎとめたいところですが、そのためには様々な作業を日々卒なくこなしていく必要があります。
管理チームも少人数になることが多く、一人あたりの作業負担は結構なものになりがちです。
そこで今回はオウンドメディアの管理を効率化し、業務負担を減らすためのコツを中心にお伝えいたします。
オウンドメディアの運用業務のフローについておさらい
オウンドメディアの運用効率化にあたり、まずは主な3つの業務フローについて見ていきます。
① 「オウンドメディアコンテンツの新規企画・事前調査」
オウンドメディアに掲載する新規コンテンツを企画して、事前にアンケートを実施したり既存の他社サイトを調査したりしながら内容の方向性を決めていきます。
マネージャーや編集者など製作チームの中心的役割を果たす担当者が、実際に制作にあたるスタッフとコミュニケーションを重ねながら公開までの細かなスケジュールを決めていきます。
② 「オウンドメディアコンテンツの内容の制作・編集」
新しく掲載するコンテンツの大まかなテーマが決まったら、テキスト・画像・動画などといったコンテンツの素材を準備していきます。
WEBライター・イラストレーター・カメラマン・動画編集者など素材の種類によって様々な担当者に作業が割り振られるため、それぞれの担当者が連絡をとりあうことでスムーズに素材の準備を進めることが重要です。
③ 「オウンドメディアコンテンツのアップロード・効果分析」
記事や動画といったコンテンツにLPや問い合わせページなどへの導線を設置したり、ディスクリプションなどを設定したりして公開準備を進めます。
また公開した後もコンテンツのアクセス状況を分析して改善点はないか調べたり、トラブルが起こった場合の対応処置を行ったりと様々な作業があります。
特にアクセス分析の作業は得られたデータがその後のコンテンツの方向性や内容にも活かせるため、余力があるときに忘れずに行っておきましょう。
オウンドメディアの運用を効率化するための4つのコツ
オウンドメディア運用をスムーズにこなすには「1から10まで全ての作業を1人で抱えようとしない」ということが重要です。
普段の運用業務の中から、以下のように外部の助けを借りて作業負担を減らせるものはないか見てみましょう。
コツその1 「AI技術を積極的に取り入れる」
ChatGPTやGeminiといったチャットボットサービスなどのAI技術は、オウンドメディアのコンテンツ制作のあらゆる場面に活用できます。
例えばブログ用の記事原稿を制作する場合には、以下のような使い道が挙げられます。
ターゲットに合わせた全体テーマの策定
オウンドメディアに特に来てほしいターゲットに対して、どんな内容のコンテンツを提供すれば関心を持ってくれるか、AIにアイデアを出してもらいます。
その際には「金属メーカーの製造担当者が課題に感じていそうなことを10個あげてほしい」というようになるべく具体的な内容で質問することで、より精度の高い回答が返ってきやすくなります。
コンテンツの構成や本文の作成
どんな内容を記事に盛り込めばいいか迷っている場合、記事の構成や本文をAIに作ってもらって参考例として実際の記事原稿に活用します。
また他のサイトに似たテーマのコンテンツがある場合、その内容を要約してもらうことで今手掛けているコンテンツで言及できていないものはないか、どこで差別化がはかれているかといったことをチェックできます。
他にもターゲットによって適宜温度感や語感などを変えながらテキストを生成してもらうといった使い方もあります。
文章の校正や表現の差し替え
完成した記事原稿に誤字や脱字、文章としておかしいところはないかAIに文章を見てもらい校正してもらいます。
またより伝わりやすい表現や検索結果に反映されやすい表現に差し替えられるところはないか調べてもらうことも可能です。
ほかにも英語や中国語など多言語でコンテンツを展開したい場合も、AIの自動翻訳機能により手間をかけずに翻訳された原稿を用意できます。
このようにコンテンツ制作のいたるところで活用できるAI技術ですが、後述するように誤った情報を出力してくることも少なくないので注意が必要です。
コツその2「外部業者に委託して用意してもらう」
コンテンツ用の記事原稿や画像の準備が間に合わない場合、外部業者に委託してつくってもらうという手もあります。
ライティングやイラスト制作の代行を専門的に行っている業者の中から、ネットでの評判や企業としての信頼性などを比較しながら安心して委託できるところはないか探してみましょう。
ほかにもアンケート調査やインタビューなど、コンテンツの内容に関わる情報収集も労力の観点から、外部業者に委託するのもありです。
ただし問い合わせしてきたユーザーの情報管理やオウンドメディアの運用方針の修正といった業務まで全て任せるのはやめましょう。
・関連記事
外注と内製、コンテンツ制作はどちらが適している?
コツその3「外部サイトのフリー素材を活用する」
ブログ記事やWEB動画にとってサムネ画像の見栄えは新規流入の数に大きく影響します。
ほかにもイラストやグラフといった画像はコンテンツの分かりやすさにつながり、オウンドメディアの顧客体験価値を大きく上げる要素といえます。
こうした画像を制作する際自分で一から作成する手間を省くために、外部のフリー素材サイトで提供している素材を活用するのもおすすめです。
ただしサイトによって商用利用や素材の加工利用が可能かどうかは異なってくるため、必ず利用規約は制作する前に一通り目を通しておきましょう。
・関連記事
「いらすとや」だけじゃない、使い分けたいフリー素材サイトまとめ
コツその4「CMSのプラグイン機能を活用する」
WEBサイトを効率的に管理するためのシステムであるCMS(コンテンツ管理システム)は、外部プラグインを導入することでさらに運用業務の効率化を図れるようになっています。
例えばWordPressでは、問い合わせフォームを簡単に追加できるプラグインやノーコードで複雑なテキストの装飾を施せるプラグインなどがあります。
こうしたプラグインを使いこなせるようになれば、確実にオウンドメディアの運用効率化につながります。
オウンドメディア運用を効率化する際の注意点
AIが出力した文章に含まれている情報は、全てが正しいものとは限りません。
一見すると正しそうに見えても調べてみると違っているといったものもあるため、出力した内容を記事原稿に反映させる前に内容に誤った情報はないか必ず確認しておきましょう。
またAIは質問した内容で検索してヒットしたWEBページの内容をまとめて回答を生成するため、ただ出力した内容をまとめるだけでは他のオウンドメディアとの差別化が図りにくくなってしまいます。
原稿の内容をすべてAIに頼るのではなく、できるだけ自社のコンテンツとして独自性を出せる内容も盛り込まないといけません。
効率的な運用体制を実現したオウンドメディアの事例
事例1:日本棋院「イゴセカ」
日本棋院は国内の囲碁における中心的な役割をになう団体として、囲碁人口の減少という課題に長年直面していました。
そこでより多くの方に囲碁に関心を持ってもらえるよう、若者に向けた親しみやすさが特徴のマイクロソフト「イゴセカ」を立ち上げました。
囲碁そのものだけでなく旅行や歴史などあらゆるジャンルの情報とかけあわせることで、気軽に読んでもらえるような内容を目指しています。
・関連記事
ターゲットユーザーに特化したマイクロサイト制作事例
事例2:日本言語聴覚士協会「めざせST」
日本言語聴覚士協会は言語聴覚士の職能団体として、言語聴覚士資格の知名度向上と受験者数の増加を目的としたマイクロサイト「めざせST」を立ち上げました。
このサイトをどのような方が見に来ているのかアクセス分析を行うことで、当初に想定してなかった新たなユーザー層の発見につながりました。
こうした発見を反映させながらよりユーザーの関心を得やすい内容のコンテンツを整備していくことで、サイトのユーザー数を大幅に上げることに成功しています。
・関連記事
知名度向上にむけたマイクロサイト「めざせST」の導入と成果
オウンドメディアの運用は「上手に任せる」のがカギ
オウンドメディアの担当者は普段ほかの業務を行いながら運用作業も行うことが多く、なかなかスムーズにコンテンツを制作し続けることが難しいといえます。
もし負担が大きくて思うようにコンテンツの制作が進まないという場合は、AIや外部業者などの「助け」を活用してみるのがおすすめです。
ただしAIに文章を生成してもらった場合は、嘘が混じっている可能性も少なくないので必ず誤りがないかを確認してから記事本文に活用するようにしてください。
・関連サービス
 | 業務変革を目的としたWEBサイト制作 お客様の業務の課題や目的をしっかり聞き出しながら、どのようなWEBコンテンツにしていきたいか一緒に考えることで、より大きな成果が見込めるWEBコンテンツを実現します。 |